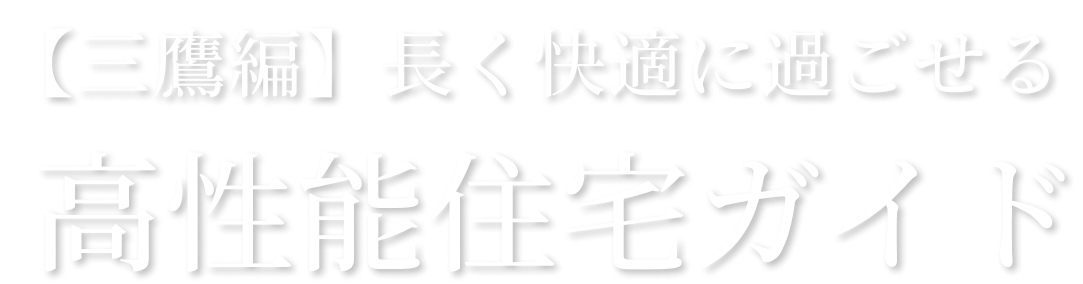「省エネ住宅」という言葉を耳にする機会が増えました。
住宅購入を検討している方の中には
「省エネ住宅って何だろう?」
「2025年から義務化されるって本当?」
と疑問を持つ方も多いでしょう。
特に、これから新築住宅を建てようとしている方にとって、この情報は避けて通れません。
本記事では、省エネ住宅の基本から種類、メリットデメリット、そして活用できる補助金まで分かりやすく解説します。
2025年の義務化に備え、あなたに最適な省エネ住宅を選ぶための知識を身につけましょう。
また、以下の記事では当メディアが厳選する高性能にこだわる住宅会社を紹介しておりますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
省エネ住宅とは?
省エネ住宅とは、エネルギー消費量を抑えるための設備や建築資材を導入した住宅のことです。
通常の住宅と比べて断熱性や気密性が高く、冬は室内の暖かい空気が逃げにくく、夏は外からの熱を遮断する効果があります。
具体的には、壁や床、天井などに十分な厚さの断熱材を入れ、窓には複層ガラスを使用するなどの工夫が施されています。
さらに高効率のエアコンや給湯器、LED照明などの省エネ設備を導入することで、住宅全体のエネルギー消費を削減するのが特徴です。
国が定めた省エネルギー基準を満たした住宅を「省エネ基準適合住宅」と呼び、これが省エネ住宅の基本形となります。
この基準を上回る性能を持つ住宅として、ZEH住宅や長期優良住宅などが存在するのです。
2025年から始まる省エネ基準義務化
2025年4月から、すべての新築住宅に対して省エネ基準への適合が義務化されます。これは2022年6月に国会で成立した建築物省エネ法の改正によるものです。
この法改正の背景には、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現があります。建築物のエネルギー消費は日本の温室効果ガス排出量の約3分の1を占めており、その削減が課題となっているのです。
義務化後は、省エネ基準を満たさない住宅は建築確認申請が通らなくなるため、実質的に建てられなくなります。
なお、住宅ローン減税については、すでに2024年1月から省エネ基準適合が条件となっています。つまり、新築住宅を建てる場合は省エネ基準への対応が今すぐに必要なのです。
省エネ住宅に求められる性能基準

省エネ住宅が満たすべき性能基準には、主に「外皮性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」の2つがあります。この2つの基準は住宅の省エネ性能を異なる観点から評価します。
そして、これらの性能は「住宅性能表示制度」によって等級で表示されるため、一般の方も理解しやすくなっています。
それぞれの基準について、以下で詳しく解説していきましょう。
外皮性能基準とは
外皮性能基準とは、住宅の断熱性能や日射遮蔽性能を評価する基準です。
「外皮」は屋根、壁、窓、床など、家全体を覆う部分を指します。この外皮の性能は主に2つの指標で評価されます。
1つ目は「外皮平均熱貫流率(UA値)」で、数値が小さいほど断熱性能が高いことを示します。これは、住宅全体の熱が外に逃げにくさを表す指標です。家全体をどれだけ「魔法瓶」のように保温できるかという性能と言えるでしょう。
2つ目は「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)」で、これも数値が小さいほど日射をしっかり遮る性能が高いことを意味します。夏場に日射による室内温度の上昇をどれだけ抑えられるかという指標です。
これらの基準値は日本の気候条件に基づき、全国を8つの地域に区分して設定されています。
一次エネルギー消費量基準とは
一次エネルギー消費量基準とは、住宅で使用されるエネルギーの総量を評価する基準です。
冷暖房、換気、給湯、照明、家電などの設備が消費するエネルギー量が対象となります。
この基準では、「BEI(Building Energy Index)」という指標を用います。BEIとは、標準的な住宅と比較してどれだけエネルギー消費量を削減できているかを示す値で、1.0以下であれば省エネ基準に適合していると判断されるのです。
さらに、太陽光発電などの創エネ設備を導入した場合は、その発電量を消費量から差し引くことが可能です。
一次エネルギー消費量の削減には、高効率給湯器やLED照明の導入、適切な換気システムの選定など、省エネ設備の活用が重要な役割を果たします。
つまり、住宅の設計段階から省エネを意識した設備選びが必要なのです。
住宅性能表示制度で確認する省エネ性能
住宅性能表示制度は、住宅の性能を客観的に評価し、等級で表示する制度です。
省エネ性能については「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」の2つの等級で表されます。
断熱等性能等級は1〜7まであり、等級4が現行の省エネ基準に相当します。2025年の省エネ基準義務化後は、新築住宅では等級4以上が必須となるのです。
一方、一次エネルギー消費量等級は1〜6まであり、等級4が省エネ基準に相当します。
これらの等級は、設計段階から消費エネルギーを計算して決定されるものです。
住宅性能表示制度を利用すると、第三者機関による客観的な評価を得られるため、省エネ性能を明確に把握できます。
住宅購入時には、この等級を確認することで、その住宅が省エネ基準に適合しているかどうかを判断できるのです。
省エネ住宅の種類

省エネ住宅には様々な種類があり、それぞれ性能基準や特徴が異なります。ここでは主な省エネ住宅の種類とその特徴について解説します。
それぞれの住宅タイプについて詳しく見ていきましょう。
省エネ基準適合住宅
省エネ基準適合住宅とは、国が定めた省エネルギー基準を満たした住宅のことです。
具体的には「断熱等性能等級4以上」かつ「一次エネルギー消費量等級4以上」という条件を満たす住宅を指します。
この住宅タイプは、2025年4月以降に新築される住宅の最低基準となります。
省エネ基準適合住宅は、従来の住宅と比べて断熱性・気密性に優れ、冷暖房のエネルギー消費を抑えられる点が特徴です。
壁・床・天井または屋根に十分な断熱材を入れ、窓には複層ガラスや断熱サッシを使用するなど、住宅全体の断熱性能を高めることが求められます。
さらに、高効率な冷暖房設備や給湯器、LED照明などを導入することで、住宅全体のエネルギー消費量を削減する設計となっているのです。
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
ZEH(ゼッチ)とは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略で、年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ以下になる住宅のことです。
ZEH住宅は高い断熱性能と省エネ設備により、通常の住宅よりエネルギー消費量を20%以上削減します。
そのうえで太陽光発電などの創エネ設備を導入し、消費エネルギーと創出エネルギーの収支をゼロ以下にするのが特徴です。
ZEHにはいくつかの種類があり、基本的なZEHのほか、省エネ基準はZEHと同等だが、創エネにより75%以上のエネルギーをまかなう「Nearly ZEH」、ZEHよりさらに省エネ性能を高めた「ZEH+」などがあります。
国は2030年度までに新築住宅の平均でZEH基準の省エネ性能確保を目指しており、補助金制度も充実しているのです。
長期優良住宅
長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことです。
長期優良住宅の認定を受けるには、省エネ性能だけでなく、耐久性・耐震性・可変性・維持管理・更新の容易性など、様々な性能要件を満たす必要があります。
省エネ性能については、2022年10月以降は「断熱等性能等級5以上」「一次エネルギー消費量等級6以上」という高い基準が求められます。
この住宅タイプの大きな特徴は、長く住み続けられる長寿命設計であることです。
定期的な点検・補修を前提とした維持保全計画の策定も必要です。
税制優遇や住宅ローンの金利優遇などのメリットがあり、長期的な視点で住宅を考える方に適した選択肢と言えるでしょう。
低炭素住宅
低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出を抑える仕組みを持つ住宅のことです。
認定基準については、2022年10月に改正が行われ、より厳しい基準が設けられました。
具体的には、一次エネルギー消費量基準が省エネ基準より20%以上の削減(BEI値0.8以下)に引き上げられ、外皮性能についても強化されています。
また、認定の必須条件として太陽光発電などの再生可能エネルギー利用設備の導入が義務付けられています。
特に戸建住宅では、省エネ量と創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であることが求められるようになりました。
低炭素住宅の認定を受けると、所得税の住宅ローン控除の控除対象限度額の引き上げや、登録免許税の軽減など、様々な税制優遇を受けられます。
その他の省エネ住宅
上記以外にも、さまざまな省エネ住宅の種類があります。中でも注目されているのは、LCCM住宅とスマートハウスです。
LCCM住宅(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅)は、建設から廃棄までの住宅のライフサイクル全体でCO2の収支をマイナスにすることを目指す住宅です。
ZEHの概念をさらに進め、住宅の建設時に排出されるCO2も考慮に入れた環境性能を持ちます。
一方、スマートハウスは、ITを活用して住宅内のエネルギー使用を最適化する住宅です。
HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)を中心に、太陽光発電や蓄電池、省エネ家電などをネットワーク化し、効率的にエネルギーを使用します。
これらの住宅タイプは、いずれも従来の省エネ住宅よりさらに高い環境性能を持ち、将来的な住宅のスタンダードになる可能性があります。
省エネ住宅のメリットとデメリット
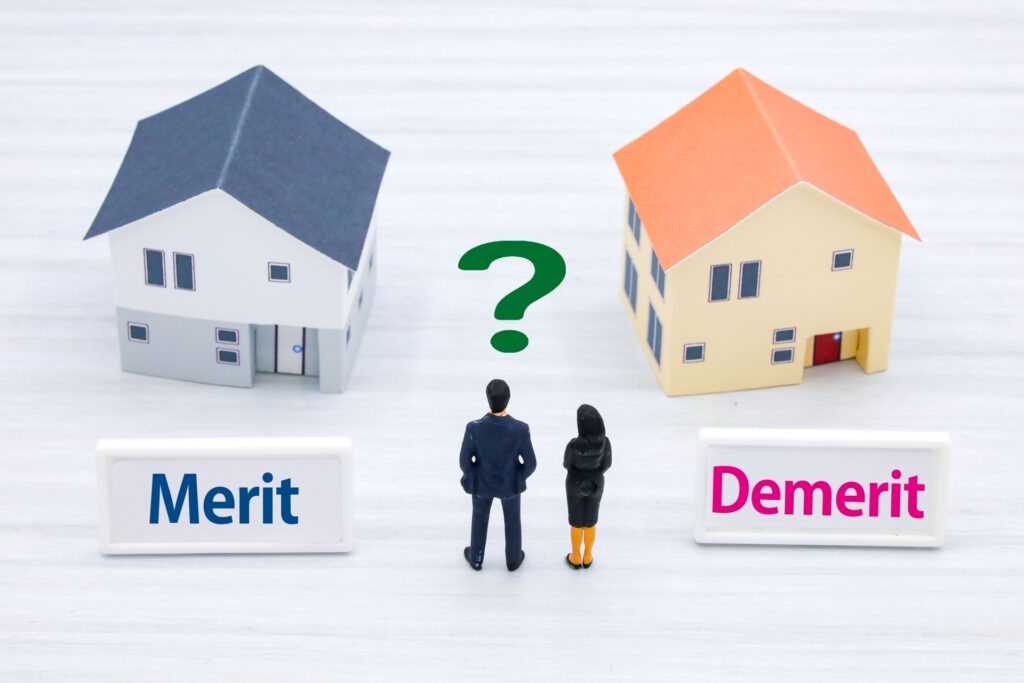
省エネ住宅を選ぶ際には、メリットとデメリットの両方を理解し、総合的に判断することが重要です。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
省エネ住宅のメリット
省エネ住宅の最大のメリットは、一年を通して快適な室内環境が得られる点です。
高い断熱性により、夏は涼しく冬は暖かい住環境が実現します。窓際や廊下、浴室などの温度差が少なくなるため、家中どこでも快適に過ごせるでしょう。
経済面では、光熱費の削減効果が期待できます。国土交通省の試算によると、省エネ基準適合住宅では一般住宅に比べて年間約2.5万円の光熱費削減が可能とされています。
健康面でも大きなメリットがあります。住宅内の温度差が小さくなることで、ヒートショックのリスクが低減されます。
さらに、結露の発生も抑えられるため、カビやダニの繁殖が防止され、アレルギー症状の緩和にも効果的です。
家族全体の健康維持にプラスとなる点も見逃せないメリットと言えるでしょう。
省エネ住宅のデメリット
省エネ住宅の最大のデメリットは、建築コストが高くなる点です。
国土交通省の試算によると、延床面積約120㎡の戸建て住宅を省エネ基準に適合させるためには、約87万円の追加コストがかかるとされています。
高性能な断熱材や窓、設備機器の導入が必要なため、一般住宅より建築費が上昇するのは避けられません。
もう一つの課題は、省エネ住宅の施工には高い技術力が必要な点です。
断熱材の施工不良や気密性の確保ができていないと、想定していた省エネ効果が得られないことがあります。
そのため、省エネ住宅の施工実績が豊富で、技術力のある業者を選ぶことが重要となるでしょう。
省エネ住宅の補助金・支援制度

省エネ住宅の普及を促進するため、国や地方自治体はさまざまな補助金や支援制度を設けています。
これらの制度を賢く活用することで、初期費用の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
こうした補助金制度は毎年内容が変更されるため、最新情報を確認することが重要です。以下で詳しく解説します。
ZEH住宅の補助金
ZEH住宅の新築・購入を検討している方には、「子育てグリーン住宅支援事業」が特におすすめです。
2025年度に新設された本制度では、特に高性能な「GX志向型住宅」が新たな補助対象として加わりました。
GX志向型住宅は、断熱等性能等級6以上かつ一次エネルギー消費量を35%以上削減する住宅で、こちらを選ぶと世帯条件に関係なく160万円の補助金が受け取れます。
ZEH水準住宅は40万円(建替時60万円)、長期優良住宅は80万円(建替時100万円)の補助が受けられるのです。
また、環境省による「戸建住宅ZEH化等支援事業」も継続して実施されており、ZEHタイプで55万円/戸、ZEH+タイプで90万円/戸の基本補助額が設定されています。
ただし、同一住宅に対して複数の補助金を併用できないケースが多いため、自分にとって最も有利な制度を選ぶことが大切です。
省エネリフォームで使える補助金
すでに住宅を所有している方は、省エネリフォームのための補助金制度を活用できます。
「先進的窓リノベ事業」は、既存住宅の窓やドアを高断熱製品に交換する際に利用できる補助金制度で、一戸あたり最大200万円の補助金が受けられます。
ガラス交換や内窓設置、外窓交換などの工事も対象となります。
「給湯省エネ事業」では、高効率給湯器への交換に対して補助金が交付されます。
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)で6万円/台などの基本補助額が設定されており、戸建住宅はいずれか2台まで補助の対象となります。
また、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、既存住宅を長期優良住宅の性能に近づけるリフォームに対して補助が行われます。
省エネ改修だけでなく、耐震改修や維持管理対策なども含む総合的なリフォームを支援する制度で、認定を受けると最大160万円の補助金が用意されているのです。
地方自治体独自の補助金
国の補助金に加え、多くの地方自治体が独自の補助金制度を設けています。これらは国の制度と併用できる場合が多く、さらに手厚い支援を受けられる可能性があります。
東京都の「東京ゼロエミ住宅」制度は、独自の環境性能基準を満たす住宅に対して最大240万円の補助金を交付しています。
2024年10月からは新基準が適用され、太陽光発電設備の設置が原則必須となりましたが、その分補助金額も大幅に増額されました。
また、補助金だけでなく不動産取得税の減免も受けられる点が特徴です。
地方自治体の補助金制度は地域ごとに内容が異なるため、お住まいの自治体のホームページで最新情報を確認するか、住宅メーカーに相談するとよいでしょう。
省エネ住宅選びの3つのポイント

省エネ住宅の購入を検討する際、どのような点に注目すべきでしょうか。ここでは、失敗しない省エネ住宅選びのポイントを3つご紹介します。
これらのポイントを押さえることで、無理のない予算で快適な省エネ住宅を手に入れられるでしょう。
自分に合った省エネ性能を選ぶ
省エネ住宅といっても、その性能レベルはさまざまです。2025年からは新築住宅に省エネ基準適合が義務化されますが、どの性能レベルを選ぶかは自分次第です。
選択のポイントは、住む地域の気候条件と家族のライフスタイルを考慮することでしょう。
北海道のような寒冷地では断熱性能が特に重要になりますが、温暖な地域では日射遮蔽性能を重視した方が快適に過ごせるかもしれません。
また、予算と将来の光熱費削減効果のバランスも考慮すべき点です。
高性能な住宅ほど初期費用は高くなりますが、長期的に見れば光熱費削減によるコストメリットが大きくなります。ライフプランに合わせて最適な選択をしましょう。
適切な省エネ設備を導入する
省エネ住宅では、断熱・気密性能に加えて、どのような設備を導入するかも重要です。
効率の良い冷暖房設備や給湯器、照明など、適切な設備選びが省エネ効果を高めます。
高効率給湯器は、従来型と比べて大幅なエネルギー削減が可能です。家族の人数や生活パターンに合わせて最適なものを選びましょう。
太陽光発電システムは、ZEHの要件の一つであり、長期的な光熱費削減に貢献します。
設置スペースや初期費用、売電価格などを考慮して導入を検討すべきです。蓄電池と組み合わせれば、災害時の電力確保にも役立ちます。
HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)は、家庭内のエネルギー使用状況を見える化し、効率的な運用をサポートします。
省エネ意識を高める効果も期待できるため、導入を検討する価値があるでしょう。
信頼できる施工業者を選ぶ
省エネ住宅の性能は、設計だけでなく施工の質にも大きく左右されます。断熱材の施工不良や気密処理の不備があると、省エネ性能を十分に発揮できません。
施工業者を選ぶ際は、ZEHビルダーの登録の有無や、省エネ住宅の施工実績が豊富かどうかをチェックすることが重要です。
さらに、アフターサポート体制も見逃せません。省エネ住宅は設備が多く、定期的なメンテナンスが必要になるケースもあります。
長期的に住宅を支えてくれるサポート体制が整っているか、事前に確認しておくと安心でしょう。
また、複数の業者から見積もりを取り、比較検討するのも大切です。省エネ性能について分かりやすく説明し、疑問に丁寧に答えてくれる業者を選ぶことで、後悔のない選択ができるでしょう。
三鷹市で注文住宅を建てるなら大創建設がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 大創建設株式会社 |
| 住所 | 東京都三鷹市上連雀7丁目32番32号 |
| 対応エリア | 三鷹市・武蔵野市・調布市・小金井市・府中市・西東京市・杉並区・練馬区・世田谷区 |
| 公式サイト | https://www.daiso1966.jp/ |
三鷹市で省エネ住宅の建築を検討しているなら、大創建設がおすすめです。
大創建設は「100年住める快適な家」をコンセプトに、高い省エネ性能と耐久性を兼ね備えた住宅を提供しています。
大創建設の特徴は、スーパーウォール工法による高気密・高断熱・高耐震構造の住宅です。
省エネ住宅の建築では、断熱性能や気密性能が鍵となりますが、大創建設はこれらの性能にこだわった家づくりを行っています。
光熱費の削減だけでなく、住み心地の良さも重視したい方は、一度相談してみる価値があるでしょう。
もし、大創建設についてもっと知りたい方は大創建設へ問い合わせてみましょう。
大創建設株式会社の口コミや評判、特徴に関して、以下の記事で詳しく解説しています。同社について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
まとめ
2025年4月からすべての新築住宅に省エネ基準適合が義務化されることで、省エネ住宅は今後のスタンダードとなります。
省エネ住宅にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。自分のライフスタイルや予算に合わせて最適な住宅を選ぶことが大切です。
また、国や地方自治体による補助金制度を活用することで、初期費用の負担を軽減できます。複数の制度があるため、どの制度が自分に最も有利かを比較検討しましょう。
省エネ住宅選びでは、自分に合った省エネ性能の選択、適切な設備の導入、信頼できる施工業者の選定が重要なポイントです。
これらを押さえることで、長期的に満足できる省エネ住宅を手に入れられるでしょう。