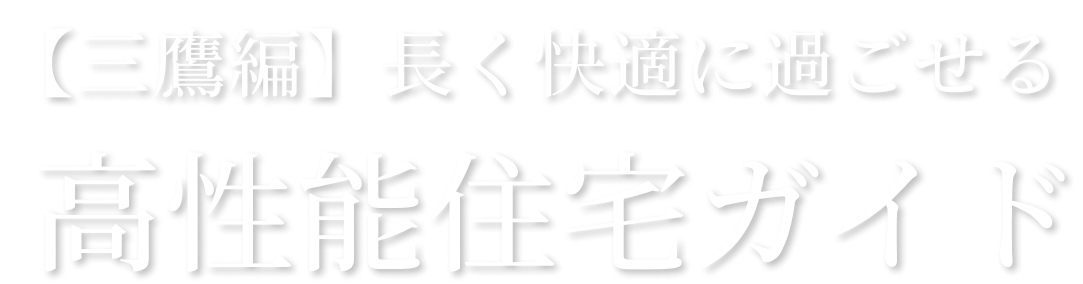「省エネ住宅を建てたいけど費用がどれくらいかかるの?
「本当に元が取れるの?」
と悩んでいませんか?
確かに省エネ住宅は通常の住宅より高額ですが、光熱費削減や各種補助金を活用すれば意外とお得かもしれません。
特に2025年4月からは全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられるため、今が検討のベストタイミングです。
本記事では省エネ住宅の費用相場を種類別に解説します。さらに2025年最新の補助金情報や投資回収期間のシミュレーションまで網羅しました。
これから省エネ住宅の新築やリフォームを考えている方に、具体的な費用と長期的なメリットを理解していただける内容となっています。
また、以下の記事では当メディアが厳選する高性能にこだわる住宅会社を紹介しておりますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
省エネ住宅の主な種類
省エネ住宅とは、断熱性・気密性を高め、エネルギー消費を抑えた住宅のことです。
主な省エネ住宅の種類には、「ZEH(ゼッチ)」「長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「LCCM住宅」などがあります。
ZEHは高い断熱性能と太陽光発電で年間のエネルギー収支をゼロにする住宅です。
長期優良住宅は省エネ性能に加えて耐久性や耐震性も優れた住宅のことで、認定低炭素住宅はCO2排出削減に重点を置いています。
LCCM住宅は、建築から解体までのライフサイクル全体でCO2排出をマイナスにする最も環境性能が高い住宅と言えるでしょう。
これらは国の推進政策によって普及が進められており、様々な補助金や税制優遇の対象となっているのが特徴です。
予算や環境への配慮、将来的なメリットを考慮して、最適な住宅タイプを選ぶことが大切です。
省エネ住宅の追加コストはいくら?
省エネ住宅は一般住宅と比較して初期費用が高くなります。これは高性能な断熱材や窓、省エネ設備などの追加コストが発生するためです。
国土交通省の試算によると、省エネ基準に適合させるために必要な追加コストは、一般的な戸建て住宅で約87万円です。
追加コストの主な内訳は、高性能断熱材が約30〜80万円、高断熱窓が約30〜100万円、高効率給湯器などの省エネ設備が約20〜50万円です。
ただし、実際の費用負担を考える際は、各種補助金や税制優遇を差し引いた「実質コスト」で判断すべきです。
また長期的には光熱費削減効果によって初期投資を回収できる点も考慮すべきでしょう。
省エネ住宅は初期費用だけでなく、長期的な視点でトータルコストを見ることが重要なのです。
省エネ住宅の種類別費用相場

省エネ住宅は種類によって必要な性能や設備が異なるため、費用も変わってきます。
主な省エネ住宅の種類別に、どれくらいの追加コストがかかるのか解説します。
省エネ住宅の選択では初期費用だけでなく、補助金や税制優遇も考慮して総合的に判断するのが賢明です。
費用対効果の高い住宅を選ぶことで、将来的な経済メリットも大きく変わってくるでしょう。
ZEH(ゼッチ)の費用相場
ZEHは、高い断熱性能と省エネ設備、そして太陽光発電を組み合わせた住宅です。一般住宅と比較すると約200〜300万円の追加費用がかかります。
主な内訳は以下の通りです。
| 項目 | 追加費用 |
|---|---|
| 高性能断熱材 | 約50〜80万円 |
| 断熱窓 | 約50〜100万円 |
| 太陽光発電システム | 約120〜170万円(4kW) |
また、ZEHはさらに「Nearly ZEH」や「ZEH Oriented」というバリエーションもあります。
こちらは太陽光発電の規模縮小や省略が可能なため、約150〜250万円程度の追加費用となるのが一般的です。太陽光発電の設置が難しい都市部の住宅向けと言えるでしょう。
長期優良住宅の費用相場
長期優良住宅は省エネ性能だけでなく、耐久性や耐震性にも優れた住宅です。一般住宅と比較すると約100〜200万円の追加費用がかかるのが一般的です。
主要なコスト増の要因は下記の通りです。
| 項目 | 追加費用 |
|---|---|
| 断熱材の強化 | 約30〜50万円 |
| 耐震等級向上のための構造補強 | 約40〜60万円 |
| 長寿命化のための高耐久材料 | 約30〜50万円 |
長期優良住宅の大きな特徴は税制優遇が充実している点です。固定資産税の減額期間が一般住宅より延長されるほか、住宅ローン減税の控除額も大きくなります。
さらに不動産取得税の特例で課税標準から1,300万円が控除されるなど、税制面のメリットも多いのです。
このような優遇措置により実質的な負担は軽減され、長期的に見れば費用対効果の高い選択になるでしょう。
認定低炭素住宅の費用相場
認定低炭素住宅は、CO2排出量を抑える環境配慮型の住宅です。一般住宅と比較して約150〜250万円の追加費用がかかります。
主な追加コストの内訳は以下の通りです。
| 項目 | 追加費用 |
|---|---|
| ZEH水準の断熱性能確保 | 約80〜120万円 |
| 節水型設備(トイレ等) | 約10〜20万円 |
| 太陽光発電システム | 約120〜170万円 |
認定低炭素住宅の特徴は、太陽光発電などの再生可能エネルギー利用設備の導入が必須となっている点です。
特に戸建住宅の場合、省エネ量と創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であることが求められます。
認定を受けると、長期優良住宅と同等の税制優遇が受けられます。
登録免許税の税率が一般の0.4%から0.1%に軽減されるほか、住宅ローン減税の控除額も最大409.5万円と、一般住宅よりも大幅に増額されます。
LCCM住宅の費用相場
LCCM住宅(ライフサイクルカーボンマイナス住宅)は、建築時から解体までのライフサイクル全体でCO2排出を削減する最先端の省エネ住宅です。一般住宅より約300〜400万円高くなるのが一般的です。
主な追加コストは以下の通りです。
| 項目 | 追加費用 |
|---|---|
| ZEH以上の断熱・気密性能 | 約100〜150万円 |
| 太陽光発電システム | 約150〜200万円(5kW以上) |
| 高効率設備(給湯等) | 約30〜50万円 |
LCCM住宅は国土交通省の推進事業の対象となっており、最大140万円の補助金が受けられます。
環境性能が最も高い住宅タイプで、将来的な省エネ規制強化にも対応できる先進的な住宅です。
太陽光発電による売電収入や電力の自給自足によって、長期的には大きな経済メリットも期待できる点が魅力と言えるでしょう。
省エネリフォームの種類別費用

既存住宅を省エネ化するリフォームの費用相場を解説します。
省エネリフォームは断熱性能の向上と設備の高効率化という2つのアプローチがあり、それぞれ費用対効果が異なります。
省エネリフォームは全面的に行うと高額になりますが、部分的に実施することも可能です。
補助金制度も充実しているため、効果的に活用すれば費用負担を抑えられるでしょう。
断熱リフォームの費用相場
断熱リフォームとは、壁・床・天井などに断熱材を設置して住宅の断熱性能を高める工事です。部位によって費用が大きく異なり、全体的に工事すると高額になります。
断熱リフォームの部位別費用は次の通りです。
| 部位 | 費用目安 | 工期 |
|---|---|---|
| 天井・床の断熱材充填 | 4,000〜8,000円/㎡ | 2〜4日 |
| 外壁への断熱パネル貼り | 3,000〜5,000円/㎡ | 1〜4週間 |
| 外壁への断熱材施工 | 4,000〜3万円/㎡ | 2〜4週間 |
一戸建て住宅ですべての断熱リフォームを行った場合、約300万〜600万円が目安となるでしょう。
費用は高額になりますが、「子育てグリーン住宅支援事業」などの補助金が適用されます。
断熱リフォームは冷暖房効率を大幅に向上させる効果があり、特に築年数が古い住宅ほど効果が高い傾向にあります。
窓の断熱リフォーム費用
窓の断熱性能を高めるリフォームは、費用対効果が高い省エネ対策として注目されています。
住宅の熱の出入りは窓からが最も多いため、窓の断熱改修で大きな省エネ効果が期待できるのです。
窓の断熱リフォーム方法と費用は以下の通りです。
| 工法 | 費用目安 | 工期 |
|---|---|---|
| ガラス交換(Low-E複層ガラス等) | 2万〜8万円/枚 | 1日 |
| 内窓の設置 | 8万〜30万円/箇所 | 1〜2日 |
| 外窓サッシの交換 | 15万〜50万円/箇所 | 2〜3日 |
窓の断熱リフォームは「先進的窓リノベ事業」の補助対象となっており、最大200万円の補助金が受けられます。
特に内窓の設置は、既存の窓枠を活かしたまま二重窓にできるため、比較的安価で効果が高い方法として人気があります。
一般的な住宅で内窓を全面的に設置する場合、100万円前後の費用で大幅な断熱性能向上が見込めるでしょう。
省エネ設備導入の費用相場
省エネ設備の導入は、電気やガスなどのエネルギー消費を直接削減する効果があります。
特に給湯器は家庭のエネルギー消費の約3割を占めるため、高効率タイプへの交換で大きな節約効果が期待できるのです。
主な省エネ設備の導入費用は以下の通りです。
| 設備 | 費用目安 | 工期 |
|---|---|---|
| エコキュート(ヒートポンプ給湯器) | 30万〜50万円 | 1〜2日 |
| エコジョーズ(ガス給湯器) | 25万〜40万円 | 1日 |
| エネファーム(家庭用燃料電池) | 150万〜200万円 | 1〜2日 |
| 太陽光発電システム | 120万〜170万円 | 1週間 |
| 蓄電池システム | 150万〜200万円 | 1〜2日 |
これらの設備は「給湯省エネ事業」などの補助金対象となっております。
太陽光発電と蓄電池の組み合わせは初期費用が高額ですが、電力の自給自足や売電収入によって長期的には大きなメリットがあるでしょう。
【2025年度版】省エネ住宅の最新支援制度

2025年度も省エネ住宅やリフォームに対する国の支援制度が充実しています。省エネ性能向上に取り組む住宅所有者に対して手厚い補助が用意されています。
これらの支援制度は併用も可能なため、うまく活用すれば初期投資の負担をかなり軽減できるでしょう。
各制度の申請時期や条件をしっかり確認し、計画的に利用することが重要です。
子育てグリーン住宅支援事業
子育てグリーン住宅支援事業は、2024年度の「子育てエコホーム支援事業」の後継制度で、省エネ住宅の新築やリフォームに対して補助金を交付します。
新築の場合は子育て世帯や若者夫婦世帯が対象で、長期優良住宅は80万円、ZEH水準住宅は40万円の補助が受けられます。
さらに、全世帯を対象にGX志向型住宅なら最大160万円の補助が可能です。
リフォームの場合は、「開口部の断熱改修」「外壁・屋根・床の断熱改修」「エコ住宅設備の設置」のうち2つ以上を行うことが条件です。
補助額は工事内容に応じて最大40万円、すべての必須工事を実施すると最大60万円まで引き上げられます。
それぞれ条件があるため、注意が必要です。補助金には予算が限られているため、早めの申請を検討しましょう。
先進的窓リノベ2025事業
先進的窓リノベ2025事業は、窓の断熱改修に特化した補助金制度です。断熱窓への改修工事費用を最大200万円まで補助してくれる手厚い支援策と言えるでしょう。
補助対象となる工事は、ガラス交換や内窓の設置、外窓交換です。補助金額は製品の性能区分や窓の大きさによって詳細に設定されています。
ただし、ドアの交換だけ、またはドアへの内窓設置だけの工事は補助対象外なので注意が必要です。
この制度の魅力は、窓という費用対効果の高い部分に絞って大きな補助が受けられる点にあります。
窓は住宅の熱損失の約5〜6割を占めるため、断熱改修の効果が最も高く感じられる部位と言えるでしょう。
申請は対象製品を取り扱うリフォーム業者が行うため、事前に業者の対応可否を確認することが重要です。
給湯省エネ2025事業
給湯省エネ2025事業は、高効率給湯器の導入を支援する補助金制度です。
家庭のエネルギー消費の約3割を占める給湯を省エネ化することで、大きな光熱費削減効果が期待できます。
補助金の対象となる設備は、ヒートポンプ給湯機(エコキュート)が60,000円/台、ハイブリッド給湯機が80,000円/台、家庭用燃料電池(エネファーム)が160,000円/台です。
特に注目すべきは、古い給湯器からの買い替えで追加補助が受けられる点です。蓄熱暖房機を撤去すれば80,000円/台、電気温水器を撤去すれば40,000円/台が加算されます。
高効率給湯器は省エネ効果が目に見えやすく、10年前の機器から買い替えると年間約2〜3万円の光熱費削減効果が期待できるでしょう。
住宅ローン減税の優遇措置
住宅ローン減税は省エネ性能によって控除額が大きく変わる仕組みとなっています。
2025年度税制改正では、住宅ローン減税の優遇措置が省エネ性能と世帯区分によって細分化されました。
控除額は年末のローン残高に0.7%を乗じた金額で、控除期間は新築で13年間です。
子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額は、認定長期優良住宅・低炭素住宅で5,000万円、ZEH水準で4,500万円、省エネ基準適合で4,000万円です。
その他世帯はそれぞれ4,500万円、3,500万円、3,000万円となります。
2024年以降に建築確認を受ける住宅は省エネ基準適合が必須条件となり、環境配慮と少子化対策を推進する制度設計になっています。
省エネ住宅の経済的メリット

省エネ住宅は初期費用こそ高いものの、長期的には様々な経済的メリットがあります。
省エネ住宅への投資は単なる出費ではなく、長期的な資産形成の一環として捉えることが大切です。
具体的な数字で見ると、その経済的合理性がより明確になるでしょう。
省エネ住宅に住むとどれくらい節約できる?
省エネ住宅に住むことで実現する光熱費削減効果は住宅の種類によって異なります。
国土交通省の試算によると、省エネ基準に適合した住宅では、一般的な戸建て住宅で年間約2.5万円の光熱費削減効果があるとされています。
ZEH住宅の場合はさらに大きな削減効果が期待できます。環境共創イニシアチブの調査によると、ZEH住宅の年間エネルギー購入額は平均17.6万円ですが、売電収入が平均11.7万円あるため、実質的なエネルギーコストは年間5.9万円になります。
エネルギーの購入額や日照時間などの要因によって影響を受けますが、売電によって家計の負担が軽くなっていることは確かです。
省エネ住宅の導入コストを何年で回収できる?
省エネ住宅の追加コストを光熱費削減でどれくらいの期間で回収できるのかを考えてみましょう。
省エネ基準適合住宅の場合、追加コスト約87万円に対して年間2.5万円の光熱費削減となるため、単純計算で約35年かかります。しかし、補助金や減税を活用すると実質負担額は大幅に減少します。
ZEH住宅の場合、追加コスト200〜300万円に対して年間の光熱費削減・売電収入合計が約15〜20万円とすると、10〜20年で回収できる計算です。
ここに最大100万円の補助金や住宅ローン減税の優遇を加味すると、実際の回収期間は7〜15年程度に短縮されるでしょう。
今後の電気料金上昇を考慮すると、実際の回収期間はさらに短くなる可能性も高いのです。
省エネ住宅の将来的な価値はどうなる?
省エネ住宅は将来的な資産価値の観点からも優位性があります。
2025年4月から新築住宅には省エネ基準適合が義務付けられるため、今後は省エネ性能が住宅の必須条件となります。
このため、既に省エネ基準以上の性能を持つ住宅は、中古市場でも評価されやすい傾向にあるのです。
国土交通省の調査によると、省エネ性能が高い住宅は中古市場での価格下落率が小さいという結果が出ています。
特に長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅は、一般住宅と比較して資産価値の減少率が10〜20%ほど小さいとされています。
不動産鑑定評価においても省エネ性能が重視される傾向が強まっており、将来的な住宅投資として非常に理にかなった選択と言えるでしょう。
省エネ住宅のコストで見落とされがちな費用

省エネ住宅の費用を検討する際、初期建築コストや光熱費削減効果は注目されますが、意外と見落とされがちな費用もあります。
長期的な視点で総コストを把握するためには、これらの隠れた費用も考慮が必要です。
これらの費用を事前に把握しておくことで、想定外の出費を防ぎ、より現実的な資金計画を立てられます。
省エネ住宅のメリットを最大限に活かすためにも、総合的なコスト把握が重要なのです。
補助金や認定にかかる手続き費用
省エネ住宅の各種認定取得や補助金申請には、審査費用や申請代行料などの手続き費用がかかる場合があります。
これらは初期費用として計上されないことも多く、見落としがちなポイントです。
主な認定・評価制度にかかる費用は、長期優良住宅認定で5〜15万円、BELS評価書取得のための費用で5〜10万円、住宅性能評価の費用で7〜20万円です。
これらの費用は住宅の規模や地域によって変動し、建築費用に含まれているケースも多いでしょう。
補助金申請も同様に、申請手続きの代行料が発生することがあります。見積もり段階で手続き費用の有無を確認しておくと安心です。
予想外の出費を避けるためにも、事前に総費用を把握しておくことが大切でしょう。
省エネ設備の維持や交換にかかるコスト
省エネ設備は初期導入費用だけでなく、将来的なメンテナンスや機器交換のコストも考慮する必要があります。
特に太陽光発電システムや高効率給湯器などの設備は、一定期間後の更新が必要になるのです。
また定期的なメンテナンス費用として、太陽光パネルの清掃や点検費用なども必要です。
これらのランニングコストを考慮せずに初期費用と光熱費削減効果だけで判断すると、長期的な収支計画が甘くなる可能性があるでしょう。
特に太陽光発電システムはパワーコンディショナーの交換が10〜15年で必要になることが多く、この費用を見込んでおくことが重要です。
三鷹市で注文住宅を建てるなら大創建設がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 大創建設株式会社 |
| 住所 | 東京都三鷹市上連雀7丁目32番32号 |
| 対応エリア | 三鷹市・武蔵野市・調布市・小金井市・府中市・西東京市・杉並区・練馬区・世田谷区 |
| 公式サイト | https://www.daiso1966.jp/ |
三鷹市エリアで省エネ住宅を建てるなら、大創建設が高い評価を受けています。
大創建設の省エネ住宅は『100年住める快適な家』をコンセプトに、経済性と住み心地を両立させた住まいを提供しています。
特にスーパーウォール工法による高気密・高断熱構造は、省エネ性能と耐震性を兼ね備えた理想的な住宅と言えるでしょう。
省エネ住宅で快適な暮らしを実現したい方は、一度相談してみると良いでしょう。
もし、大創建設についてもっと知りたい方は大創建設へ問い合わせてみましょう。
大創建設株式会社の口コミや評判、特徴に関して、以下の記事で詳しく解説しています。同社について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
まとめ
省エネ住宅は一般住宅より初期費用が高くなりますが、光熱費削減や各種補助金を活用すれば長期的にはお得な選択と言えます。
2025年から省エネ基準適合が義務化されるため、今後は標準となる住宅性能です。
「子育てグリーン住宅支援事業」「先進的窓リノベ2025事業」「給湯省エネ2025事業」などの補助金制度を賢く活用すれば、初期投資の負担を軽減できます。
ただし、申請手続き費用や設備の将来的な交換コストなど見落としがちな費用も考慮する必要があります。
総合的な視点で判断し、自分に合った省エネ住宅を選ぶことが大切です。長期的な資産価値も高く維持される省エネ住宅は、未来への投資として価値ある選択と言えるでしょう。