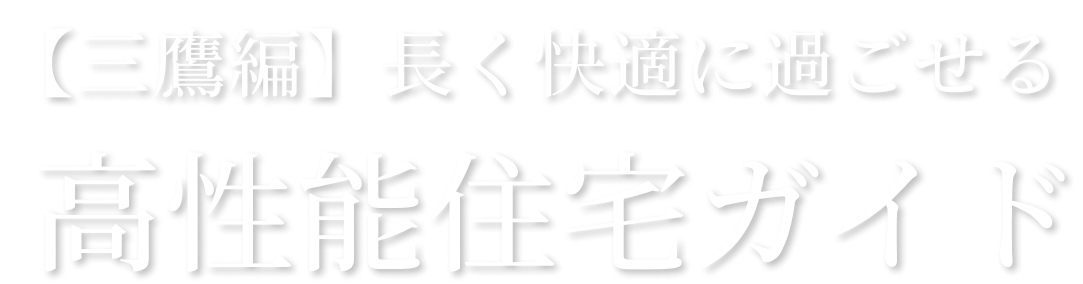マイホーム購入を検討中の皆さん、「2025年から省エネ基準が義務化される」というニュースをご存知でしょうか。
この変更により新築住宅の性能要件が大きく変わるため、多くの方が
「具体的に何が変わるの?」
「どんな住宅を選べばいいの?」
と不安を感じているはずです。
本記事では、省エネ基準の内容から住宅の種類、確認方法、そして経済的メリットまで徹底解説します。
これから家づくりを始める方が賢い選択をするための情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。
2025年省エネ基準義務化の全容

2025年4月から全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務化されます。
この変更は日本のエネルギー政策と環境対策の一環として進められているもので、住宅購入を検討している方には重要な情報です。
具体的にどのような背景があり、どう変わるのか見ていきましょう。
省エネ基準義務化は、単なる規制強化ではなく、快適な住環境の実現と地球環境保全の両立を目指す取り組みです。これから詳しく解説していきます。
省エネ基準義務化の背景
省エネ住宅基準の義務化は、「2050年カーボンニュートラル」という国の目標達成に向けた重要施策の一つです。
日本では住宅・建築物部門が全エネルギー消費の約3割を占めており、この分野での省エネ対策が急務となっています。
2022年6月には建築物省エネ法が改正され、住宅の省エネルギー性能向上に向けた法整備が進みました。
これまでは大規模な建築物のみに適用されていた省エネ基準適合義務が、2025年4月からはすべての新築住宅にも拡大されるのです。
国際的にも日本の住宅の断熱性能は欧米諸国と比較して低く、エネルギー効率の向上は国際競争力の面からも重要な課題でした。
この基準義務化によって、住宅の質的向上と環境負荷の軽減が同時に実現できるでしょう。
2025年から住宅はどう変わる?
2025年4月以降、新築住宅には省エネ基準への適合が義務付けられます。
具体的には「断熱等性能等級4以上」かつ「一次エネルギー消費量等級4以上」という条件を満たす必要があるのです。
最も大きな変化は建築確認申請時の審査プロセスでしょう。2025年4月以降に申請する新築住宅では、省エネ性能の適合性審査が必須となります。この審査に通らなければ、住宅の建築ができなくなるのです。
小規模な住宅や増改築部分にも基準適合が求められるため、影響範囲は非常に広いと言えます。
これにより、省エネ性能の低い住宅は市場から姿を消し、全ての新築住宅で一定水準以上の省エネ性能が確保されることになるでしょう。
省エネ基準適合住宅の条件

省エネ基準適合住宅とは、国が定める省エネルギー性能の基準をクリアした住宅のことです。
具体的には、断熱性能と使用エネルギー量の2つの観点から基準が設けられており、さらに地域ごとに異なる数値基準が適用されます。
これらの基準を理解することで、自分が検討している住宅が省エネ基準を満たしているかどうかを判断できるようになります。
断熱等性能等級4とは?
断熱等性能等級は、住宅の断熱性を評価する指標です。等級は1〜7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを意味します。
省エネ基準適合住宅の条件となる「等級4」は、冷暖房に使用するエネルギーを大幅に削減できる水準と言えるでしょう。
この等級は主に「UA値」という数値で評価されます。UA値とは「外皮平均熱貫流率」のことで、住宅の壁や屋根、床、窓などの外皮全体からどれだけ熱が逃げやすいかを示す値です。
数値が小さいほど断熱性能が高く、熱の出入りが少ない住宅と判断できます。
断熱等性能等級4は、1999年に制定された「次世代省エネ基準」に相当するもので、住宅の開口部も含めた断熱対策が必要となります。
2022年4月に等級5〜7が新設されるまでは最高等級でしたが、現在では「省エネ基準適合の最低ライン」という位置づけです。
一次エネルギー消費量等級4とは?
一次エネルギー消費量等級は、住宅で使用するエネルギーの総量を評価する指標です。
等級は3〜6まであり、数字が大きいほどエネルギー効率が良いことを示します。省エネ基準を満たすには「等級4以上」が必要です。
この等級は「BEI」という指標で評価されます。BEIとは、標準的な住宅のエネルギー消費量と比較して、設計段階の住宅がどれだけエネルギーを使うかの比率を表すものです。
一次エネルギー消費量等級4はBEI値が1.0以下、つまり基準と同等かそれ以下のエネルギー消費であることを意味します。
等級5はBEI値0.9以下で基準より10%以上削減、等級6はBEI値0.8以下で基準より20%以上削減と定められており、高い等級ほどエネルギー効率の良い住宅と言えるでしょう。
地域別の省エネ基準値
日本は地域によって気候条件が大きく異なるため、省エネ基準も地域ごとに設定されています。
全国は1〜8の8つの地域区分に分けられ、寒冷地ほど厳しい断熱基準が求められるのです。
断熱性能を示すUA値は、地域によって基準値が異なります。同様に、日射の遮蔽性能を示すηAC値(平均日射熱取得率)も、地域ごとに異なる基準が設けられています。
| 地域区分 | 主な該当都道府県 | 断熱等級4のUA値 | ηAC値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道北部 | 0.46以下 | – |
| 2 | 北海道南部 | 0.46以下 | – |
| 3 | 青森、岩手 | 0.56以下 | – |
| 4 | 宮城、新潟 | 0.75以下 | – |
| 5 | 東京、愛知 | 0.87以下 | 3.0以下 |
| 6 | 大阪、福岡 | 0.87以下 | 2.8以下 |
| 7 | 宮崎、鹿児島 | 0.87以下 | 2.7以下 |
| 8 | 沖縄 | – | 6.7以下 |
自分の居住地域に適した省エネ基準を確認し、それに合った性能の住宅を選ぶことが大切です。
地域区分は国土交通省のウェブサイトで確認できるので、住宅購入前に必ずチェックしましょう。
省エネ住宅の3つの主要タイプ

省エネ基準適合住宅の中でも、さらに性能の高い住宅が存在します。
ここでは代表的な3つのタイプを紹介します。
これらの住宅タイプは省エネ基準適合住宅より厳しい条件を満たしていますが、その分、住環境の質や経済的メリットも大きくなる傾向にあります。
ZEH住宅
ZEH(ゼッチ)とは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略称で、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指した住宅です。
高い断熱性能と省エネ設備で使用エネルギーを削減し、太陽光発電などで創エネすることで、エネルギー収支ゼロを実現します。
ZEH住宅の基準は「断熱等性能等級5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級6以上」と、省エネ基準適合住宅より高いレベルに設定されています。
ZEHには複数の区分があり、削減率や条件によって「ZEH」「Nearly ZEH」「ZEH Ready」「ZEH Oriented」などに分類されます。
ZEH住宅は2030年度までに新築住宅の標準になることが政府の目標として掲げられており、今後の住宅市場の主流になると予想されるでしょう。
長期優良住宅
長期優良住宅とは、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」として認定された住宅です。
省エネ性能だけでなく、耐久性や耐震性、可変性、維持管理のしやすさなど、総合的な住宅の質が評価されます。
省エネ性能に関しては、2022年の基準改正により「断熱等性能等級5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級6以上」という高い水準が求められるようになりました。これはZEH住宅と同等の省エネ性能を意味します。
長期優良住宅の認定を受けるには、住宅の劣化対策や耐震性なども含めた基準をすべて満たす必要があります。
認定を受けた長期優良住宅は、住宅ローン控除の上限額引き上げや不動産取得税の控除額増額など、多くの税制優遇措置を受けられるため、初期コストは高くても長期的には経済的なメリットが大きい住宅と言えるでしょう。
低炭素住宅
低炭素住宅とは、CO2排出量削減に配慮した住宅のことで、令和4年10月に基準が強化されました。
現在は省エネ基準より20%以上のエネルギー削減が必要で、「断熱等性能等級5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級5以上」という条件が求められます。
認定には強化外皮基準の達成に加え、再生可能エネルギー利用設備の導入が必須となっています。
さらに節水対策、ヒートアイランド対策、V2H充放電設備設置など9項目から1つ以上を実施する必要があります。
認定を受けると住宅ローン控除の拡充や不動産取得税の軽減などの税制優遇が適用され、環境面と経済面の両方でメリットがある住宅タイプです。
省エネ基準適合の確認方法

住宅が省エネ基準に適合しているかどうかを確認するには、いくつかの公的な評価書や証明書を確認する方法があります。
これらの書類は住宅ローン減税などの申請時にも必要となるため、新築住宅を購入する際には必ず確認しておきましょう。
住宅性能評価書で確認する
住宅性能評価書は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく第三者評価制度によって発行される公的な証明書です。
この評価書では「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」の2項目で省エネ性能を確認できます。
省エネ基準適合住宅であれば、断熱等性能等級が4以上、一次エネルギー消費量等級も4以上と表示されているはずです。
住宅性能評価には「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2種類があり、両方の評価書があるとより安心です。
取得には費用がかかりますが、公的な第三者機関による評価であるため信頼性が高く、住宅ローン減税申請にも利用できる点が大きなメリットと言えるでしょう。
BELS評価書で確認する
BELS(ベルス)は「建築物省エネルギー性能表示制度」の略称で、住宅の省エネ性能を第三者機関が評価・認証する制度です。
省エネ性能を★(1つ星)から★★★★★(5つ星)までの5段階で表示するため、視覚的にわかりやすいのが特徴です。
BELS評価では★★が省エネ基準適合レベル、★★★がZEH Ready相当、★★★★以上がNearly ZEH・ZEH相当となります。
評価書にはBEI値やUA値などの具体的な数値も記載されています。
BELS評価書は住宅性能評価書より費用が安く取得しやすいため、省エネ性能だけを証明したい場合に適した選択肢と言えるでしょう。住宅ローン減税の申請にも利用可能です。
その他の省エネ証明書類で確認する
住宅性能評価書やBELS評価書以外にも、省エネ基準適合を証明する書類があります。
「住宅省エネルギー性能証明書」は登録住宅性能評価機関等が発行する証明書で、住宅ローン減税申請に利用できます。
「建築物省エネ法に基づく適合性判定通知書」や「建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書」も省エネ基準適合を示す公的書類です。
ZEH住宅なら「ZEH支援事業の交付決定通知書」等、長期優良住宅や低炭素住宅は「認定通知書」の有無が重要な確認ポイントでしょう。
これらは住宅の性能を客観的に証明するもので、購入検討時には不動産会社や住宅メーカーに確認することをお勧めします。
省エネ住宅の5つのメリット

省エネ住宅は単に法律の基準を満たすだけでなく、住む人にとって多くのメリットをもたらします。
以下に主な5つのメリットを紹介します。
省エネ住宅のメリットは、入居後すぐに実感できるものから長期的なものまで様々です。これから詳しく見ていきましょう。
健康リスクの低減
省エネ住宅の高い断熱性能は、私たちの健康を守る重要な役割を果たします。
一般的な住宅では、冬場に部屋ごとの温度差が大きくなりがちですが、断熱性の高い住宅ではこの温度差が小さくなります。
特に注目すべきは「ヒートショック」の予防効果です。ヒートショックとは、暖かいリビングから寒い浴室へ移動する際などに、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こすリスクのことです。
厚生労働省の統計によると、入浴中の急死者は年間約1万9千人にのぼると言われており、その多くがヒートショックに関連すると考えられています。
省エネ住宅では室内の温度差が少ないため、このリスクを大幅に低減できるのです。このような健康面での安心感が省エネ住宅の大きな魅力と言えるでしょう。
快適な室内環境の実現
省エネ住宅は高い断熱性と気密性により、一年を通して快適な室内環境を実現します。
従来の住宅では、夏は暑く冬は寒い環境になりがちですが、省エネ住宅では外気温の影響を受けにくいため、季節を問わず快適に過ごせるのです。
もう一つの大きなメリットは結露の防止効果です。壁や窓の表面温度が室温に近づくため、結露が発生しにくくなります。
結露はカビやダニの発生原因となるため、アレルギー疾患の方にとっては特に重要なポイントでしょう。
さらに、高気密住宅では計画的な換気システムが導入されるため、外部からの花粉や粉塵の侵入を抑えながら新鮮な空気を取り込めます。
これにより、アレルギー症状の軽減や空気質の向上が期待でき、優しい住環境を提供するのです。
光熱費の大幅削減が可能
省エネ住宅は、その名の通り大幅な省エネルギー効果をもたらします。断熱性・気密性の向上により冷暖房効率が高まるため、エネルギー消費量を抑えられるのです。
具体的な削減効果として、省エネ基準適合住宅は従来の住宅と比べて約20%の冷暖房エネルギー削減が見込まれます。
さらに、ZEH住宅では約30%以上の削減効果があるとされているのです。
これに照明や給湯などのエネルギー効率化も加えると、さらに大きな削減効果が得られるでしょう。
光熱費削減は毎月の家計に直接影響するため、住宅ローン返済中の家計負担を軽減する効果もあります。
長期的に見れば、省エネ住宅の初期投資は光熱費削減によって回収できる計算なのです。
補助金制度を活用して負担を軽減
省エネ住宅の購入や建築には、様々な補助金制度を活用できます。
2025年現在、特に注目すべきは「子育てグリーン住宅支援事業」でしょう。この制度では、省エネ性能の高い新築住宅の購入や省エネリフォームに対して補助金が交付されます。
新築住宅の場合、GX志向型住宅で最大160万円、長期優良住宅で80万円、ZEH住宅で40万円の補助金が受けられます。
補助金制度は年度ごとに内容が変わることがあるため、最新情報をチェックすることが重要です。
これらの補助金を活用することで、省エネ住宅の建築・購入にかかる初期費用の負担を大きく軽減できるため、住宅計画の際には必ずチェックしておくべきでしょう。
税制優遇で長期的にお得に
省エネ住宅には様々な税制優遇措置があり、長期的に大きな経済的メリットをもたらします。特に大きいのは住宅ローン減税の優遇です。
2025年に入居する新築住宅の場合、借入限度額は省エネ性能によって大きく異なります。
長期優良住宅・低炭素住宅は4,500万円、ZEH水準住宅は3,500万円、省エネ基準適合住宅は3,000万円となっています。
これに対し、省エネ基準を満たさない住宅は新築の場合、原則として住宅ローン減税の対象外です。
その他にも不動産取得税の軽減や、登録免許税の軽減など、様々な税制優遇があります。
固定資産税も長期優良住宅は5年間1/2に減額されるなど、省エネ住宅を選ぶことで長期的な税負担が大きく軽減されるのです。
三鷹市で注文住宅を建てるなら大創建設がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 大創建設株式会社 |
| 住所 | 東京都三鷹市上連雀7丁目32番32号 |
| 対応エリア | 三鷹市・武蔵野市・調布市・小金井市・府中市・西東京市・杉並区・練馬区・世田谷区 |
| 公式サイト | https://www.daiso1966.jp/ |
省エネ基準に適合した高性能な住宅を建てるなら、大創建設がおすすめです。
大創建設は『100年住める快適な家』を理念に、スーパーウォール工法による高気密・高断熱・高耐震住宅を提供しています。
1年を通して快適で、将来の省エネ基準強化にも対応可能な家づくりが特徴です。
省エネ基準に対応した住宅をお考えなら、ぜひ一度大創建設に相談してみてはいかがでしょうか。
もし、大創建設についてもっと知りたい方は大創建設へ問い合わせてみましょう。
大創建設株式会社の口コミや評判、特徴に関して、以下の記事で詳しく解説しています。同社について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
まとめ
2025年4月から全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務化され、「断熱等性能等級4以上」かつ「一次エネルギー消費量等級4以上」が必要になります。
ZEH住宅や長期優良住宅などの高性能住宅は、健康面・快適性・経済性で大きなメリットがあります。
購入時には住宅性能評価書やBELS評価書で性能を確認し、補助金や税制優遇も活用しましょう。
今後も基準強化が予想されるため、単に最低基準を満たすだけでなく、長期的視点での住宅選びが重要です。