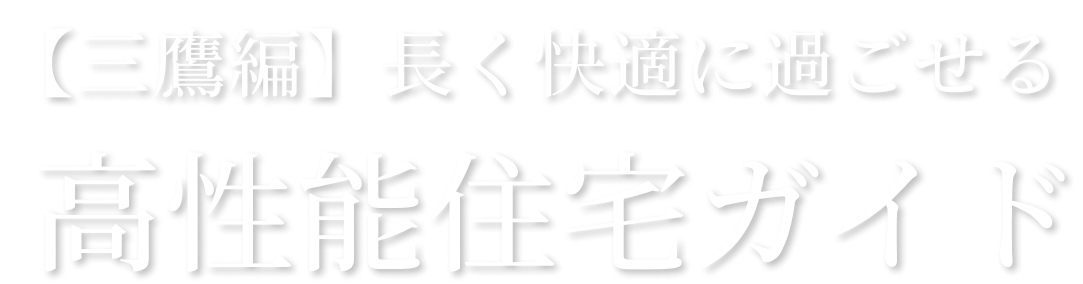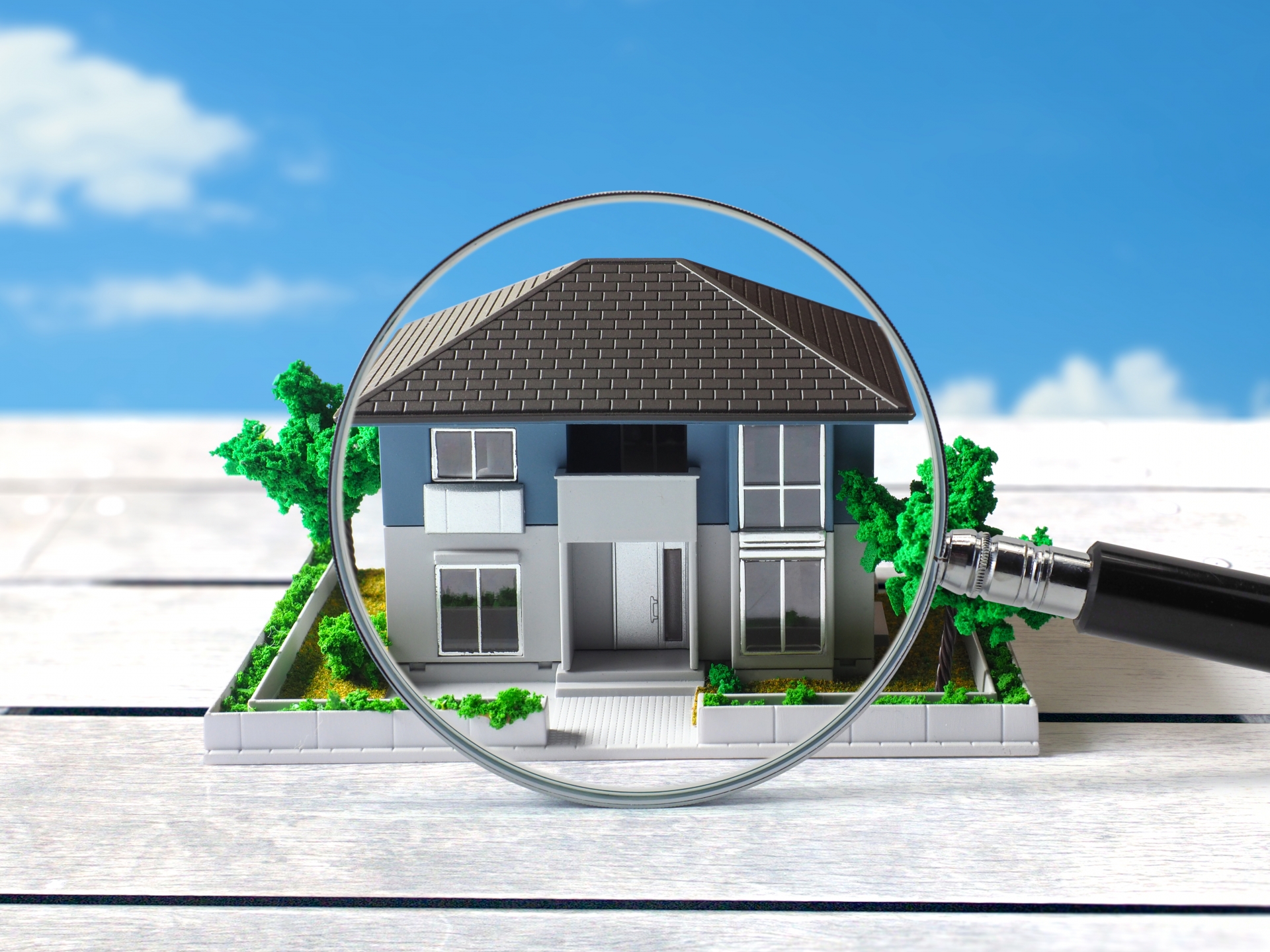「家の中が寒い」
「冬の光熱費が高すぎる」
とお悩みではありませんか?
実は日本の住宅は、海外に比べて断熱性能が低いものが多いのです。
2025年4月からは「次世代省エネ基準」の適合が全ての新築住宅で義務化されます。この基準をクリアすれば、一年中快適な室温で過ごせる上、光熱費の削減にもつながるでしょう。
さらに、将来的な住宅の資産価値にも大きく影響します。
本記事では、次世代省エネ基準の内容から対策方法まで、あなたの住まい選びに役立つ情報を徹底解説します。
また、以下の記事では当メディアが厳選する高性能にこだわる住宅会社を紹介しておりますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
次世代省エネ基準とは?
次世代省エネ基準とは、平成11年(1999年)に制定された住宅の省エネルギー性能を示す基準です。
正式には「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等の判断の基準」と呼ばれています。
この基準は壁や天井だけでなく、窓やドアなどの開口部にも断熱材の使用を求めるもので、現在の住宅性能表示制度における「断熱等性能等級4」に相当します。
外壁や屋根、床などの外皮全体の断熱性能を「UA値」という指標で評価し、地域ごとの気候条件に応じた基準値が設定されているのが特徴です。
住宅の省エネ基準はどう変わってきたか
住宅の省エネ基準は時代とともに段階的に強化されてきました。
最初の基準は1980年に「旧省エネ基準」として制定されました。その後、1992年には「新省エネ基準」が登場し、断熱性能の要求水準が引き上げられました。
続いて1999年には「次世代省エネ基準」が制定され、さらに高い断熱性能が求められるようになったのです。
2013年には評価方法が大きく変わり、「一次エネルギー消費量」という新たな指標も加わりました。
そして2016年の基準では、建築物省エネ法に基づく現行の省エネ基準が確立されています。
2025年から始まる省エネ基準適合義務化

2025年4月から全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務化されます。この改正は日本の住宅の省エネ性能を底上げし、温室効果ガス削減に貢献する重要な転換点です。
義務化について詳しく見ていきましょう。
この義務化により、日本の住宅の最低基準が引き上げられ、より快適で省エネ性能に優れた住環境が広がると予想されます。
義務化される省エネ基準の内容
義務化される省エネ基準には、「断熱等性能等級4」と「一次エネルギー消費量等級4」の二つの基準があります。
断熱等性能等級4は、住宅の断熱性能を表す指標で、外皮平均熱貫流率(UA値)で評価されます。UA値は数値が小さいほど断熱性能が高いことを示し、地域ごとに基準値が設定されています。
一方、一次エネルギー消費量等級4は、住宅で使用されるエネルギー量を評価する指標です。暖冷房、換気、給湯、照明などに使用されるエネルギー消費量を総合的に評価し、基準一次エネルギー消費量以下であることが求められます。
これらの基準を満たすには、適切な断熱材の使用や高効率設備の導入が必要です。基準適合のための具体的な対策は、後ほど詳しく解説します。
省エネ基準適合義務化のスケジュール
省エネ基準適合義務化は、段階的に進められてきました。
2021年4月には、300㎡以上の中規模住宅に対して適合義務化が始まり、2022年10月からは、300㎡未満の小規模住宅に対して建築主への説明義務が強化されました。
そして2025年4月からは、全ての新築住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられます。この義務化により、建築確認申請時に省エネ基準への適合を証明する必要があり、これを満たさない場合は建築確認が下りないことになるのです。
さらに、2030年頃には現在の断熱等性能等級4(次世代省エネ基準)から、より厳しい断熱等性能等級5(ZEH水準)への引き上げが検討されています。
このため、現時点で等級5以上の性能を持つ住宅を選ぶと、将来的な基準強化にも対応でき、資産価値の維持にもつながるでしょう。
義務化の対象となる建築物の範囲
省エネ基準適合義務化の対象は、2025年4月以降に着工する全ての新築住宅です。
一戸建て住宅だけでなく、マンションやアパートといった共同住宅も含まれ、規模を問わず全ての住宅建築物が対象となります。
ただし、一部例外もあります。平屋かつ床面積が200㎡以下の住宅で、都市計画区域・準都市計画区域の外に建てられる場合は、適合性審査が不要とされています。
既存住宅については、新たに増築や改築を行う場合、その部分についてのみ省エネ基準への適合が求められますが、既存部分については遡って基準適合を求められることはありません。
ただし、断熱等性能等級4未満の既存住宅は、将来的に増改築や売買が難しくなる可能性もあるため、リフォーム時に断熱性能を向上させることも検討すべきでしょう。
断熱等性能等級の拡充

2022年に住宅性能表示制度が改正され、断熱等性能等級が大きく拡充されました。これにより、より高性能な住宅の基準が明確になりました。
新しい断熱等級について詳しく見ていきましょう。
ZEH水準の省エネ性能を実現する等級5
断熱等性能等級5は、2022年4月に新設された基準で、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に相当する断熱性能です。
ZEHとは、高い省エネ性能と再生可能エネルギーにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅のことです。
等級5の住宅は、地域区分によって異なる厳しいUA値基準を満たす必要があります。例えば東京などの6地域では、UA値0.6以下が求められます。これは等級4の0.87と比べて約30%も断熱性能が向上した水準です。
具体的な断熱仕様としては、天井に吹き込み用グラスウール18K 210mm、壁に高性能グラスウール16K 105mm、床には高性能グラスウール24K 42mmと80mmの組み合わせなどが例として挙げられます。
これらの断熱材を適切に施工することで、冬暖かく夏涼しい快適な住環境が実現するでしょう。
HEAT20のG2基準に対応する等級6
断熱等性能等級6は、2022年10月に新設された基準で、民間団体HEAT20が提唱するG2グレードに相当します。
この等級では、暖冷房にかかる一次エネルギー消費量を約30%削減できる断熱性能が求められます。
等級6の住宅が達成すべきUA値は、東京などの6地域で0.46以下です。これは等級4と比較すると約47%も断熱性能が向上した水準であり、かなり高い断熱性能と言えるでしょう。
断熱仕様の具体例としては、壁の外側に押出法ポリスチレンフォーム3種 25mmを組み合わせるなど、内外両面からの断熱対策が必要になります。
これほどの高断熱住宅では、冬季の暖房費が大幅に削減され、室内の温度ムラも少なくなり、ヒートショックのリスクも低減します。
最高水準の断熱性能を誇る等級7
断熱等性能等級7は、2022年10月に新設された最高レベルの基準で、HEAT20のG3グレードに相当します。
この等級では、暖冷房にかかる一次エネルギー消費量を約40%削減できる極めて高い断熱性能が求められます。
等級7の住宅が達成すべきUA値は、東京などの6地域で0.26以下という厳しい基準です。これは等級4と比較すると約70%も断熱性能が向上した水準であり、欧州の高断熱住宅に匹敵する性能と言えるでしょう。
断熱仕様としては、高密度で厚みのある断熱材の使用が必要です。床には内外両側にフェノールフォーム 100mmを施工するなど、徹底した断熱対策が求められます。
等級7レベルの高断熱住宅では、少ないエネルギーで一年中快適な室温を維持でき、光熱費の大幅削減と健康で快適な住環境の両立が可能になります。
日本と世界の省エネ基準の差

日本の住宅断熱基準は、欧米諸国と比較すると大きく遅れをとっています。
世界と日本の断熱基準について見ていきましょう。
この差を埋めるため、日本でも近年急速に基準の見直しが進められていますが、まだ道のりは長いと言えるでしょう。
欧米諸国の住宅断熱基準
欧米諸国では、日本よりもはるかに厳しい断熱基準が設けられています。最大の違いは、欧州諸国が居住者の健康という観点から「最低室温規定」を定めている点です。
例えば、ニューヨーク州では賃貸住宅のオーナー向けの規定として、6時〜22時の間は室温20℃、22時から翌朝6時までの間は室温13℃以下にならないよう定めています。
これは、寒い住環境が居住者の健康に悪影響を及ぼすという認識に基づいています。
ドイツでは約3〜5年ごとに基準を改定し、要求水準を高めてきました。その結果、断熱性能は日本よりはるかに高く、現在の日本の基準はドイツの1984年から1995年の間くらいのレベルに相当します。
日本の断熱基準はどう進化していく?
日本の断熱基準は、今後急速に進化していくと予想されます。
2025年の省エネ基準適合義務化に続き、2030年頃には断熱等性能等級5(ZEH基準)への引き上げが検討されています。
政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すと宣言し、2030年には温室効果ガス排出量を2013年比で46%削減する目標を掲げています。
HEAT20のような民間団体の活動も基準向上に貢献しています。この団体は居住者の健康性や快適性を重視し、等級6や等級7に相当するG2、G3といったグレードを提案しています。
今後は省エネ基準の段階的な引き上げに加え、既存住宅の断熱改修を促進する施策も強化されるでしょう。
補助金や税制優遇などのインセンティブを活用しながら、日本の住宅の断熱性能は徐々に欧州水準に近づいていくと予想されます。
次世代省エネ基準をクリアする方法

次世代省エネ基準(断熱等性能等級4)をクリアするには、適切な断熱対策が必要です。断熱性能は住宅全体で考えるべきもので、部分的な対策だけでは不十分です。
基準をクリアするための主な対策は次の通りです。
これらの対策を総合的に行うことで、快適な住環境と省エネ性能の両立が可能になるでしょう。
適切な断熱材を選ぶ
断熱等性能等級4を達成するには、適切な断熱材の選定が重要です。断熱材には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
グラスウールは、ガラス繊維を綿状に加工した断熱材で、価格が比較的安く施工しやすいのが特徴です。
高性能グラスウールは密度を示す「K」の数値が大きいほど断熱性能が高くなります。例えば16K、24Kなどがあり、数値が大きいほど高性能です。
押出法ポリスチレンフォームは、発泡スチロールの一種で、防水性・耐久性に優れています。床下や基礎断熱に適しており、湿気の影響を受けにくい特性を持っています。
フェノールフォームは、熱伝導率が低く薄い厚みでも高い断熱効果が得られるため、壁の中など限られたスペースでの使用に適しています。
断熱材の施工では、断熱材同士の隙間ができないよう注意が必要です。隙間があると、断熱性能が大幅に低下する原因となるでしょう。
開口部の断熱対策をする
住宅の熱損失は窓やドアなどの開口部からが最も大きいため、断熱等性能等級4を達成するには、高性能なサッシとガラスの組み合わせが必要です。
アルミサッシは熱を伝えやすいため、断熱性能を高めるにはアルミ樹脂複合サッシや樹脂サッシの採用がおすすめです。
アルミ樹脂複合サッシは外側がアルミ、内側が樹脂でできており、耐久性と断熱性を両立しています。樹脂サッシはさらに断熱性が高く、結露防止にも効果的です。
ガラスは、単板ガラスではなく、複層ガラスを選びましょう。複層ガラスとは、2枚以上のガラスの間に空気層を設けたもので、「Low-Eガラス」と組み合わせるとさらに断熱効果が高まります。
Low-Eガラスとは、特殊な金属膜をコーティングしたガラスで、夏は日射熱をカット、冬は室内の熱を外に逃がしにくくする効果があります。
気密性を確保する
断熱性能を十分に発揮させるには、気密性の確保も欠かせません。
気密性とは、建物の隙間から空気が漏れにくい性能のことです。気密性が低いと、どれだけ断熱材を入れても効果が半減してしまいます。
気密性を高めるには、気密シートや気密テープの施工が重要です。壁や屋根の内側に気密シートを隙間なく施工し、継ぎ目を気密テープでしっかり塞ぎます。
特に注意が必要なのは、配管や配線が通る穴、コンセントボックス周り、窓枠と壁の取り合い部分などです。
また、気密性の高い住宅では適切な換気計画も必要になります。24時間換気システムなどを設置し、室内の空気を常に新鮮に保つことが大切です。
気密性能は「C値」という指標で表され、数値が小さいほど気密性が高いことを示します。C値2.0cm²/m²以下程度を目指すと良いでしょう。
住宅の断熱性能を見極めるコツ

住宅の断熱性能は目に見えない部分だからこそ、しっかりと確認することが大切です。
断熱性能の見極め方について詳しく見ていきましょう。
これらのポイントを押さえておくことで、長く快適に暮らせる住まい選びができるようになります。
新築住宅の断熱性能を確認する方法
新築住宅の断熱性能を確認するには、いくつかの重要なポイントがあります。
まず、建築士やハウスメーカーに「設計UA値」を尋ねましょう。この数値が小さいほど断熱性能が高いことを示します。
住宅性能評価書も重要な確認資料です。この評価書には断熱等性能等級が明記されており、等級4以上であれば次世代省エネ基準をクリアしています。さらに等級5以上であれば、より高性能な住宅と言えるでしょう。
設計図書や仕様書も確認すべきポイントです。どのような断熱材がどの程度の厚さで使われているか、サッシの種類や窓ガラスの仕様はどうなっているかを確認します。
また、建築中の現場検査も非常に有効です。断熱材が隙間なく施工されているかなど、工事中にしか確認できない部分があるため、第三者機関による検査も検討すると良いでしょう。
中古住宅の断熱性能を見抜く方法
中古住宅の断熱性能を見抜くには、まずは築年数から判断する方法があります。概ね以下のような目安で考えることが可能です。
| 新築時期 | 断熱性能 |
|---|---|
| 1980年以前の住宅 | 断熱等性能等級1相当(断熱性能は低い) |
| 1980〜1992年の住宅 | 断熱等性能等級2相当(旧省エネ基準) |
| 1992〜1999年の住宅 | 断熱等性能等級3相当(新省エネ基準) |
| 1999年以降の住宅 | 断熱等性能等級4相当の可能性あり(次世代省エネ基準) |
ただし、過去にリフォームされている場合もあるため、断熱リフォームの有無や内容について、売主や不動産会社に質問しましょう。
また、住宅の状態から断熱性能を推測することも可能です。窓の結露が多い、冬の室内が寒いといった症状があれば、断熱性能が低いと言えます。
専門家による診断も有効な方法です。赤外線カメラを使った調査で断熱材の有無や断熱欠損部分を確認できるため、中古住宅購入前の調査として検討すると良いでしょう。
高断熱住宅を得意とする会社を選ぼう
高断熱住宅を実現するには、その分野に詳しいハウスメーカーや工務店を選ぶことが重要です。
会社選びのポイントとしては、まず標準仕様の確認が挙げられます。標準で断熱等性能等級5以上を採用している会社なら、高断熱住宅への理解と施工技術を持っていると考えられます。
施工実績も重要な判断材料です。過去の施工事例や顧客の声を確認し、実際に高断熱住宅の施工経験が豊富かどうかを見極めましょう。
また、断熱施工の品質管理体制も確認しましょう。第三者機関による施工検査を取り入れている会社は、施工品質に対する意識が高いと言えます。
施工中の写真記録や気密測定の実施なども、品質へのこだわりを示す指標になるでしょう。
三鷹市で注文住宅を建てるなら大創建設がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 大創建設株式会社 |
| 住所 | 東京都三鷹市上連雀7丁目32番32号 |
| 対応エリア | 三鷹市・武蔵野市・調布市・小金井市・府中市・西東京市・杉並区・練馬区・世田谷区 |
| 公式サイト | https://www.daiso1966.jp/ |
三鷹市で高断熱・高気密の注文住宅をお考えなら、大創建設への相談がおすすめです。
大創建設は「100年住める快適な家」をコンセプトに、次世代省エネ基準を大きく上回る断熱性能の住宅を提供しています。
スーパーウォール工法を採用することで高断熱・高気密・高耐震の住宅づくりを実現し、断熱等性能等級5以上の住宅を標準仕様としています。
省エネ基準の義務化を見据えた住宅づくりをお考えの方は、一度相談されてみてはいかがでしょうか。
もし、大創建設についてもっと知りたい方は大創建設へ問い合わせてみましょう。
大創建設株式会社の口コミや評判、特徴に関して、以下の記事で詳しく解説しています。同社について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
まとめ
本記事では次世代省エネ基準について解説してきました。
2025年4月からはすべての新築住宅に省エネ基準適合が義務化され、断熱等性能等級4以上が求められます。
さらに2030年頃には等級5への引き上げも検討されており、日本の住宅断熱基準は着実に進化しています。
高い断熱性能を持つ住宅は、快適な室内環境と省エネ効果を両立し、健康面でも大きなメリットがあります。
新築・中古を問わず住宅選びの際は、断熱性能をしっかり確認することが大切です。
将来のことを考えるなら、現時点で等級5以上の性能を持つ住宅を選ぶことで、資産価値の維持と快適な住環境を長期的に享受できるでしょう。