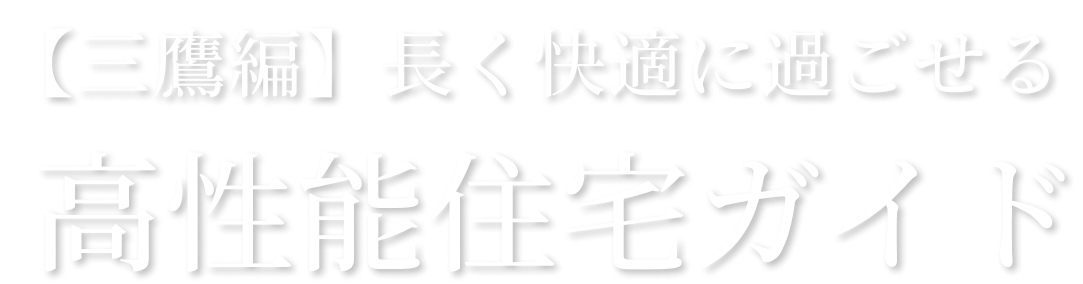「高気密住宅って実際どうなの?」
「酸欠になるって噂は本当?」
この記事を読んでいるあなたは、このような気持ちなのではないでしょうか?
大事なマイホームづくりに失敗しないために、情報はしっかり集めておきたいはずです。
この記事ではそもそも高気密住宅がどんなものかを解説し、メリット・デメリット、実際の口コミ評判まで、詳しく紹介します。
高気密住宅と高断熱住宅の違い
『高気密住宅』と『高断熱住宅』は、どちらも快適な室内環境を実現するための住宅性能を指す言葉ですが、それぞれが担う役割には明確な違いがあります。両者はセットで語られることが多いものの、意味をしっかり理解しておくことで、住宅選びの際の判断材料になります。
高断熱住宅とは
高断熱住宅とは、住宅の外壁や屋根、床、窓などに高性能な断熱材を用いて、外気の影響を受けにくくした住宅のことです。冬は室内の暖かさを外に逃がさず、夏は外の暑さを遮ることで、年間を通して室内温度を快適に保ちやすくなります。
断熱性が高いことで、冷暖房の使用を最小限に抑えることができ、省エネ性能の向上にもつながります。断熱性能は『UA値(外皮平均熱貫流率)』という数値で示され、値が小さいほど熱が逃げにくい住宅となります。
高気密住宅との違い
高気密住宅とは、住宅の隙間を極力なくして、空気の出入りをコントロールしやすくした住宅のことを指します。建物全体のすき間面積を表す『C値(相当隙間面積)』が小さいほど、気密性が高いとされます。
高断熱住宅が『熱の出入りを防ぐ』のに対し、高気密住宅は『空気の出入りを防ぐ』ことが目的です。気密性が高いことで冷暖房効率が向上するだけでなく、計画的な換気がしやすくなり、快適で清潔な空気環境を保つことができます。
つまり、高断熱は“温度”を守り、高気密は“空気”を守るという役割の違いがあり、この両方を備えて初めて、省エネ性と快適性を兼ね備えた住宅になります。
高気密住宅とは?認定される基準は?
高気密住宅とは隙間が少ない家のことです。隙間が少ないと冷暖房が効きやすく、光熱費の削減につながります。
住宅の気密度は『C値』というもので示し、『住宅全体の隙間の合計面積÷延べ床面積』で求めます。
高気密住宅に国の基準はありませんが、多くのメーカーはC値1.0㎠/㎡以下の住宅を『高気密住宅』と謳っています。ちなみに、一般的な住宅のC値はおよそ10㎠/㎡、たとえば延床面積が120㎡の家であれば、1,200㎠の隙間があるということです。つまり、20×30㎝もの大きな穴が開いているのと同じということです。
C値の計測は職人の仕事の丁寧さが反映される数値といわれています。つまり、信頼できる住宅メーカーであるかを確認する指標でもあるでしょう。
高気密住宅の5つのメリット
続いて、高気密住宅のメリットを5つ紹介します。
高気密住宅のメリットは以下5つです。
上記5つの高気密住宅のメリットを、それぞれ詳しく紹介します。
①ランニングコストの削減
高気密住宅は光熱費をかなり抑えられます。隙間が少ないため冷暖房が効きやすいのです。エアコンの設定温度が高めでも夏は涼しく、冬は暖房をつければすぐにあたたかくなります。
『高気密+高断熱』の組み合わせは冷暖房の効率を格段に上げてくれます。外部の温度を遮断して部屋を暖めても、隙間だらけだとそこから熱は逃げてしまいます。気密性があることで断熱性の効果が生きるのです。
高断熱・高気密の最高基準である『省エネ基準ZEH』の住宅は一般的な住宅と比べ、年間123,963円の光熱費をカットできます。
②結露ができにくい
高気密住宅の2つめのメリットは結露ができにくいことです。健康に悪かったり、家の寿命を短くしたりと、結露は人と家に悪影響を与えます。
空気中の水分量が多いと窓などに発生する結露。結露がカビになり、そのカビにダニが繁殖します。カビには発がん性物質が含まれていたり、ダニはアレルギーのもとになったりします。
さらに、建材部分に結露ができると木が腐ってしまうため、住宅の寿命が減ったり白アリが発生したりしてしまいます。
気密性が高いと外気が入る隙間がないため、湿度の高い梅雨時でも結露ができる心配がありません。高気密住宅は、結露から家や人を守ってくれます。
③ひとにやさしい
高気密住宅は健康に良い住環境を作ります。花粉やハウスダストの有害物質、気温差が原因のヒートショックから人を守ります。
有害な物質をたくさん取り込むとアレルギーは発症します。花粉をたくさん取り込むと花粉症になるように、ダニの虫体や死骸、抜け殻や糞をたくさん取り込むとダニアレルギーになってしまいます。
高気密住宅は花粉やPM2.5などが含まれる外気を遮ります。さらに、湿度の高い場所を好むダニを増殖させません。
また高気密住宅は、交通事故より死亡人数が多い『ヒートショック』も防ぎます。隙間が少ない高気密住宅は部屋ごとの温度差も少ないのです。急な気温変化で血圧が急激に上下し、脳に負担がかかることで起きるヒートショックも防ぎ、快適な空間を作ります。
④ヒートショック予防
高気密住宅は、家の中の温度差を抑えやすいため、ヒートショックの予防に効果的です。ヒートショックとは、急激な温度差によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳卒中を引き起こすリスクがある現象のこと。特に冬場、暖かいリビングから寒い脱衣所や浴室に移動した際に起こりやすいとされています。
高気密住宅では、隙間が少なく外気の影響を受けにくいため、室内全体の温度が安定しやすくなります。脱衣所やトイレ、廊下なども比較的暖かく保たれ、急激な温度変化が起こりにくいのが特徴です。
とくに高齢者や持病を抱える方がいる家庭では、安心して暮らせる住環境を整えるうえで、高気密住宅のヒートショック対策効果は大きなメリットとなるでしょう。
⑤高い遮音性
高気密住宅は、外部からの騒音を遮る性能が高い点も大きな魅力です。気密性が高いということは、住宅における『すき間』が少ないということ。すき間から侵入してくる外の音も同時にシャットアウトされるため、交通量の多い道路沿いや住宅密集地でも、静かな室内環境が実現します。
また、室内の音漏れも防ぎやすくなるため、音楽鑑賞やホームシアターを楽しみたい方、小さなお子様がいるご家庭にも適しています。マンションや隣家との距離が近い住宅地でも、気兼ねなく生活音を出せるのは大きな安心材料です。
快適な室内環境を求める方にとって、『静けさ』は暮らしの満足度を大きく左右する要素のひとつ。高気密住宅は、その点でも優れた性能を発揮します。
高気密住宅の5つのデメリット
高気密住宅のデメリットは以下5つです。
上記5つの高気密住宅のデメリットを、それぞれ詳しく紹介します。
①酸欠になる
高気密住宅で暮らす際の注意点としてよくあげられるのが酸欠です。隙間が少なく密閉に近い高気密住宅では「酸欠にならないの?」と懸念する方が多いです。
酸欠になると気持ち悪くなったり、息苦しくなったりします。脳が生命維持のために活動を抑えようとし、集中できなかったり、睡眠が浅くなったりという症状もあります。
実際、高気密住宅で二酸化炭素が室内に排出される石油ストーブやファンヒーターなどの『開放型ストーブ』の使用は注意が必要です。酸素不足で一酸化炭素が出る危険もあります。
高気密住宅の暖房は、電気ストーブやエアコンがおすすめです。高気密の家ならば、エアコンの暖房機能で冬も充分あたたかいです。
また、建築基準法で設置が義務付けられている『24時間換気機能』の利用や、こまめな換気でも酸欠を防げます。
②シックハウス症候群になる
建材に使用された化学物質が揮発し、その空気を吸い込むことで起きるシックハウス症候群。頭痛やめまい、吐き気や鼻水などさまざまな症状があります。
患者が国内100万人以上になるまでシックハウス症候群が増加したのは、住宅の高密度化が進んだことも一因です。密閉されている高密度住宅は、室内で発生する有害物質を家の中に閉じ込めてしまいます。
シックハウス症候群を防ぐためには『24時間換気システム』を正しく稼働させることが大事です。換気口・排気ファンが全部屋にある24時間換気システムの設置は建築法で義務付けられています。節電のため外出時にOFFし、そのまま忘れてしまうことなどがないよう注意しましょう。
他には、化学物質が発生しない建材を使用するという対処法もあり、たとえば無垢フローリングはシックハウスの発症を防ぐとして人気があります。
③エアコン設置で気密性が下がる
「高気密住宅はエアコン設置時に気密性が下がる」という意見をよく聞きます。せっかく高気密の家を建てても、エアコンの設置で気密性が落ちたら困るでしょう。
実際、設置する職人の腕によっては気密性が下がります。エアコン設置には、室内機と室外機を繋ぐために直径65㎝ほどの大きな穴を壁に開ける必要があります。通す配管に合わせて上手く穴をあけられないと気密性が下がってしまうのです。
気密性低下を防ぐには、住宅建設を依頼した住宅メーカーにエアコン設置も一緒にお願いするのがいいでしょう。高気密住宅の施工についてしっかり理解しているため、気密性に考慮して丁寧に作業してくれるはずです。専門のエアコン設置業者よりも安心して任せられます。
④住宅の建築費が高くなる
高気密住宅を建てる場合、通常の住宅よりも建築費が高くなる傾向があります。これは、気密性を確保するために、専用の部材や断熱材、高性能サッシなどを使用する必要があるためです。
また、設計段階から気密性能を考慮した施工が求められるため、職人の高度な技術と丁寧な施工が不可欠となり、その分コストが上乗せされるケースもあります。
初期費用は高くなりますが、冷暖房効率の良さや長期的な光熱費の削減によって、ランニングコストを抑えられるという利点もあります。コストと快適性のバランスをしっかりと見極めることが大切です。
⑤室内が乾燥しやすくなる
高気密住宅では外気の流入が少ないぶん、室内の空気がこもりやすくなるため、冬場は特に乾燥しやすくなる傾向があります。
これは、外との空気の入れ替えが自然に行われないことで、加湿器などで湿度管理をしないと、空気が乾いた状態になってしまうためです。
室内が乾燥すると、肌や喉の不調を引き起こすほか、ウイルスが活性化しやすくなるといった健康面のリスクもあります。特に小さなお子様や高齢者がいる家庭では、加湿器の使用や観葉植物の設置など、湿度調整の工夫が求められます。
ただし、計画換気システムと湿度管理をしっかり行えば、快適な空気環境を維持することは十分可能です。
高気密住宅のデメリット解消法
高気密住宅にはさまざまなメリットがある一方で、『酸欠』『乾燥』『シックハウス症候群』などの懸念点もあります。
これらのデメリットは、適切な対策を講じることで十分に解消できるものです。以下では、特に効果的な2つの対策についてご紹介します。
高気密住宅で快適な住環境を維持するための実践的なヒントとして、ぜひ参考にしてください。
換気システムを導入する
高気密住宅においては、計画的な換気の仕組みを整えることが非常に重要です。住宅全体の隙間が少ない構造のため、自然換気に頼ることが難しく、空気が滞留しやすくなります。これにより酸素不足や湿気・化学物質の滞留などが起こりやすくなるため、24時間換気システムの導入は必須と言えます。
特に『第1種換気システム(機械給気・機械排気)』は、温度や湿度の損失を抑えながら新鮮な空気を取り入れられるため、高気密住宅との相性が良く、快適性と省エネ性の両立が可能です。
適切な温度・湿度の管理を行う
高気密住宅では外気の影響を受けにくい反面、室内の温度・湿度を人為的にコントロールする必要があります。
特に冬場は乾燥しやすくなるため、加湿器の使用や洗濯物の室内干し、観葉植物の配置などで湿度を保つ工夫が効果的です。加えて、加湿器には温湿度センサー付きのモデルを選ぶと、過加湿を防ぎつつ快適な湿度を自動で保てるため便利です。
また、湿度が高すぎるとカビや結露の原因になるため、適切な換気と除湿対策も並行して行うことも検討しましょう。浴室やキッチンなどの水回りは特に湿気がこもりやすいため、スポット的な換気や除湿器の活用も有効です。
快適とされる室内環境は、温度20〜25℃、湿度40〜60%程度。この範囲を目安に管理することで、快適性だけでなく、健康的で清潔な住まいを維持することができるでしょう。
高気密住宅に住んでいる方の口コミ
続いて、高気密住宅に実際に住んでいる方の口コミを4つ紹介します。
ぜひ参考にして下さい。
①花粉症が良くなった
花粉症でもだえてる方増えたけど、新居に引っ越してから治ったといっても過言ではないレベルで症状出ないんだよね、小学生の頃から瀕死レベルの症状出てたのに。
高気密×第1種換気のお陰様なはずなので、温熱だけじゃない恩恵があります。
もう花粉症の薬買ってないもん。
Twitter(@SaikaMatsumoto)
②冬あたたかい
注文住宅3年目の高断熱高気密住宅だけど冬本当にあったかい。
トリプルガラスは本当にやってよかった。
実家に帰るとあまりにも寒くて身震いするけど実家もたかだか25年前の住宅なのになんでこれほどまで違いが出るのだろうか。
Twitter(@titakun)
③外の騒音が聞こえない
もちろん、外の音もほとんど聞こえないので凄く静かです
おかげで朝はよく眠れます😴
遮音性が高くて家の中も外も静か、というのも高気密住宅の良い点ですね✨
Twitter(@comfortswh)
④電気代が安い
家の建て替えてから初めての冬で全館床暖房(電気)の電気代がどのくらいになるか気になってたんだけど、1月分の電気代が1万円弱。
コンロがIHで食洗器も毎日使って、24時間床暖つけっぱで室温平均20度前後に保たれててこの電気代は正直想定外に安い。
高気密高断熱の効果凄い
Twitter(@Peacewanwan)
⑤快適な室内環境
「高断熱高気密住宅なら、22度から23度の室温で十分暖かく感じる。」
引用元:e戸建て
高気密住宅に住んでいる方々の口コミからは、『静か』『暖かい』『空気がきれい』『光熱費が抑えられる』といった生活の質が向上した実感が多く寄せられています。中でも、快適性と経済性を両立できる点に高い満足度が集まっています。
また、健康面での安心感を得られたという声も少なくありません。高気密・高断熱によって得られる省エネ性能は、電気代の削減とともに、環境負荷の低減にも貢献しており、エコ意識の高い世帯からも支持されています。
その一方で、室内が乾燥しやすい・換気を怠ると空気がこもるといったデメリットに言及する声も調査中に見受けられました。
ただ総じて、高気密住宅は『快適性』『健』『経済性』『静音性』といった複数の面で生活の質を高めてくれる住宅性能であるといえるでしょう。住み心地のよさを重視する方や、家族の健康を守りたい方、省エネ住宅に関心のある方には、非常に満足度の高い選択肢となっています。
快適な高気密住宅を建てる際の2つの注意点
良い高気密住宅を建てる際の注意点は以下2つです。
- ①窓にこだわる
- ②住宅メーカー選び
上記の高気密住宅を建てる際の注意点2つをそれぞれ詳しく紹介します。
①窓にこだわる
高気密住宅を建てる際に大事なのが窓です。なぜかというと、窓の大きさや、窓枠の素材によっては気密・断熱性が一気に下がってしまうからです。せっかく性能にこだわった住宅を建てても、窓によって光熱費のコストカット効果が低くなってしまいます。
気密・断熱性を高めようとするとどうしても窓を小さくしてしまいます。しかしあまり窓が小さいと、日差しが入らず閉鎖的な家になってしまいます。
大きな窓を設置しても気密性が落ちないよう、素材にこだわるのがいいでしょう。熱伝導率が低く頑丈な樹脂サッシなど、品質の高いものを選びましょう。
②住宅メーカー選び
高気密住宅を建てる際に最も大事なのが住宅メーカー選びです。
高気密住宅は国の定める基準がありません。極端にいうと「どんなメーカーでも高気密住宅を謳える」のです。メーカーによって高気密の基準がそれぞれ異なります。
信頼できる住宅メーカーを見分けるポイントは、C値の計測値が1.0㎠/㎡であるかです。しかしC値を計測しているメーカーは10社に1社ほどしかありません。
なぜC値を計測するメーカーが少ないのかというと、職人の技量がC値に反映されるからです。設計時に計測できる断熱性の指標UA値と違い、気密性の指標であるC値は家を建てた後に計測します。
逆にいうと、C値を計測している住宅メーカーは職人の施工の腕に自信があるということです。
三鷹市周辺で高品質な高気密住宅を建てるなら大創建設がおすすめ

三鷹市をはじめ、東京都下の住宅を幅広く手がける大創建設。機能性・品質・デザインすべてバランスよい住宅を提供します。
シンプルで洗練された北欧スタイルの住宅シリーズ『TRETTIO』、省エネの最高水準住宅『ZEH』、魔法瓶のようなあたたかさが魅力の『スーパーウォール工法』など。
『スーパーウォール工法』は、気密性を示すC値1.0㎠/㎡が基準の高気密住宅です。一邸一邸、気密測定して、結果を依頼主は確認できます。
C値は職人の仕事の丁寧さが反映される数値といわれ、職人に対しての信用が無いとなかなか計測できません。C値1.0㎠/㎡という数値は、大創建設の技術力の高さがうかがえます。
まとめ
この記事では、高気密住宅がどういうものなのかの解説や基準、メリット・デメリット、口コミ評判など、詳しく紹介しました。
高気密住宅は、隙間が少なく冷暖房がよく効くため、光熱費が削減できます。一方で隙間が少ないが故、換気しないとシックハウス症候群や酸欠の危険性も。
また、良い高気密住宅を建てるには、気密性を示す『C値』を発表しているメーカーを選ぶのがポイントです。高気密住宅は国が基準を定めていないため、誰でも高気密を謳えるからです。
この記事が、高気密住宅を検討している方の参考に、少しでもなれば幸いです。