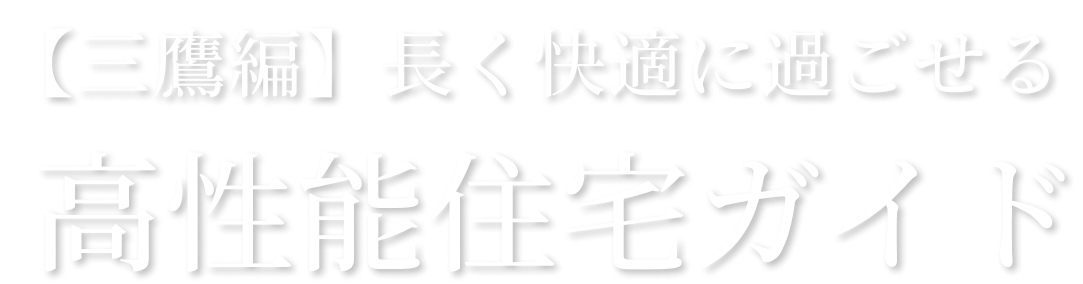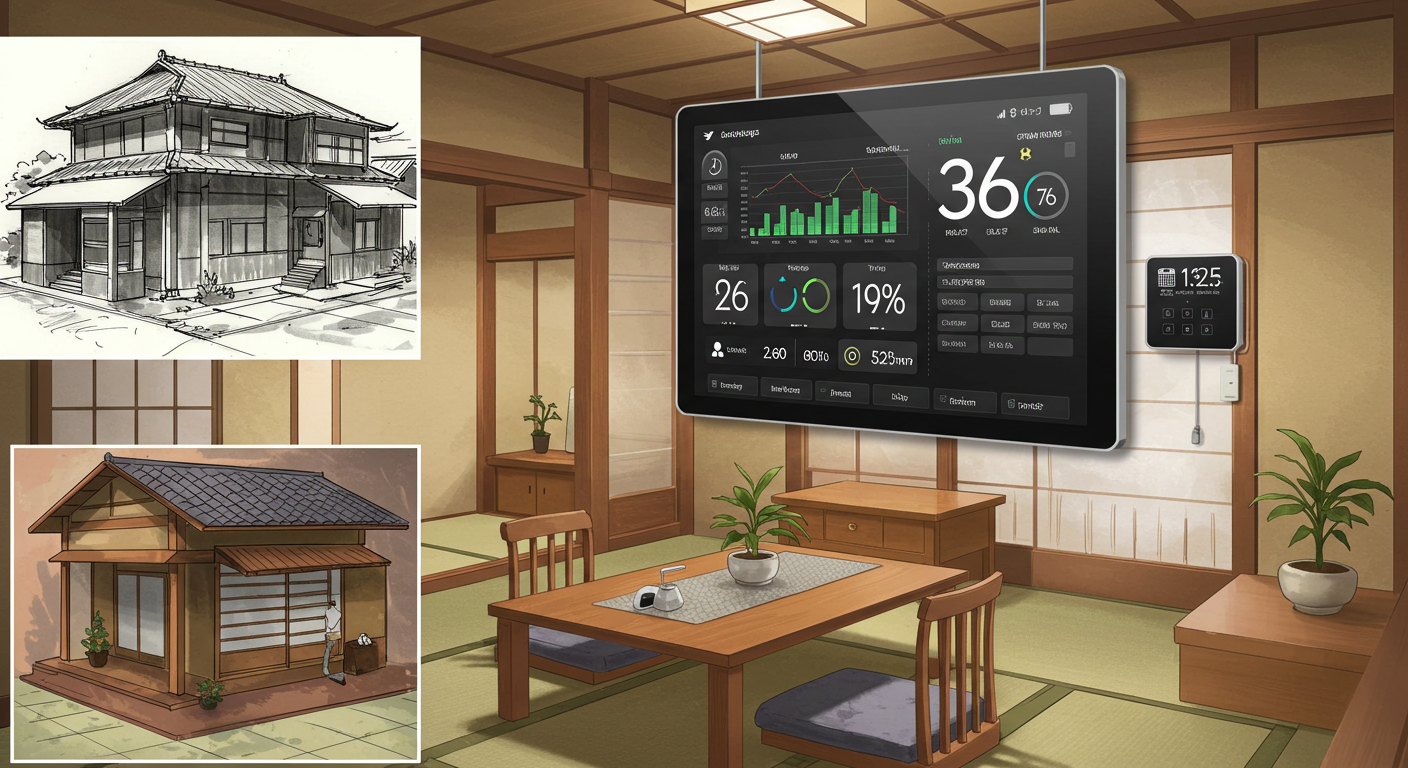住宅は人生で最も高額な買い物の一つです。そのため、性能や品質について客観的に評価された住宅を選ぶことは非常に重要です。
住宅性能表示制度は、住宅の基本的な性能を公正に評価し、住まい選びをサポートする制度として活用されています。これから新築住宅の購入を検討している方は、必ず確認しておきたい制度です。
そこで、本記事では住宅性能表示制度について解説します。合わせて、メリットやデメリットも解説するので参考にしてください。
また、以下の記事では当メディアが厳選する高性能にこだわる住宅会社を紹介しておりますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度は、2000年に施行された『住宅の品質確保の促進等に関する法律』に基づく制度です。国土交通省が定めた客観的な評価方法により、構造耐力や火災安全性などの住宅の基本的な性能を評価します。
評価は第三者機関が行うため、住宅の品質を公平に判断することができます。新築住宅だけでなく、既存住宅の性能評価も行うことができる制度となっています。
住宅性能評価の10項目を解説
- 構造の安定に関すること
- 火災時の安全に関すること
- 劣化の軽減に関すること
- 維持管理・更新への配慮に関すること
- 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
- 空気環境に関すること
- 光・視環境に関すること
- 音環境に関すること
- 高齢者等への配慮に関すること
- 防犯に関すること
住宅性能評価制度では、住まいの基本的な性能を上記10項目に分けて評価します。各項目は等級で評価され、数値が大きいほど性能が高いことを示します。
新築住宅の購入を検討する際は、特に重視したい項目を明確にし、総合的な性能を確認することが大切です。
構造の安定に関すること
地震に対する強さや地盤の安定性を評価する項目です。等級は1から3まであり、数値が高いほど耐震性に優れています。
等級3は極めて稀に発生する大地震に対しても、倒壊や崩壊する可能性が低い性能を有することを示します。新耐震基準を満たす一般的な住宅は等級2相当となっています。
火災時の安全に関すること
火災発生時の安全性を評価する項目です。内装材の燃えにくさや延焼を防ぐ性能、避難経路の確保などを総合的に判断します。等級は1から4まであり、数値が高いほど火災に対する安全性が高くなります。
特に寝室や階段など、避難時に重要となる場所の安全性が重視されます。
劣化の軽減に関すること
建物の耐久性を評価する項目です。主要構造部分である床や壁、屋根などが長期間の使用に耐えられるかを判断します。等級は1から3まであり、等級3は通常の維持管理を行えば、おおむね75年~90年までの長期使用に対応できる性能を有することを示します。
維持管理・更新への配慮に関すること
設備配管の点検や修繕のしやすさを評価する項目です。給排水管やガス管などの配管の維持管理のしやすさを評価します。等級は1から3まであり、等級が高いほど配管の点検や修理が容易にできる構造となっています。
将来的な修繕やリフォームの際の作業性も考慮されます。
温熱環境・エネルギー消費量に関すること
住宅の断熱性能や冷暖房の効率性を評価する項目です。壁や窓、床、天井などの断熱性能が高いほど、室内温度を快適に保ちやすく、冷暖房費用の削減にもつながります。
等級は1から5まであり、等級が高いほど省エネ性能が優れていることを示します。
空気環境に関すること
室内の空気環境の快適さを評価する項目です。換気設備の性能や内装材からの化学物質の放散量を評価します。等級は1から3まであり、等級が高いほど室内の空気環境が優れています。
24時間換気システムの性能や、ホルムアルデヒドなどの有害物質への対策が評価のポイントとなります。
光・視環境に関すること
窓の大きさや配置による採光性能を評価する項目です。自然光の取り入れやすさや、窓からの眺望の確保などを評価します。等級は1から4まであり、等級が高いほど採光や眺望の性能が優れています。
日当たりの良さは住まいの快適性に大きく影響するため、重要な評価項目となっています。
音環境に関すること
外部騒音に対する遮音性能や、室内の遮音性能を評価する項目です。等級は1から4まであり、等級が高いほど音の伝わりにくさに優れています。
特に寝室や居間など、生活の中心となる空間での静けさを確保する上で重要です。交通量の多い道路に面している場合は、特に注意が必要です。
高齢者等への配慮に関すること
バリアフリー性能を評価する項目です。段差の解消や手すりの設置、廊下や出入り口の幅などを評価します。等級は1から5まであり、等級が高いほど高齢者や障害者にとって使いやすい住宅となっています。
将来的な身体機能の低下に備えて、長期的な視点で検討することが重要です。
防犯に関すること
住宅の防犯性能を評価する項目です。開口部(窓やドア)の侵入防止性能を評価します。等級による評価ではなく、防犯対策の有無を確認する仕組みとなっています。
防犯性の高い建物部品(CP部品)の使用や、センサーライトの設置なども評価のポイントとなります。
住宅性能表示制度を利用するメリット
住宅性能表示制度を利用することで、住宅の品質を客観的に評価できます。第三者機関による公平な評価のため、住宅メーカーや工務店の言葉だけでなく、数値として性能を確認できます。
また、評価書があることで、保険料の割引や優遇金利を受けられる可能性があり、経済的なメリットも期待できます。
第三者機関による審査で住宅性能が可視化される
住宅性能評価は、国土交通大臣が指定した第三者機関が実施します。そのため、住宅会社とは利害関係のない中立的な立場から、客観的な評価を得ることができます。
評価結果は数値で示されるため、異なる住宅との性能比較も容易になり、自身の希望する性能水準に合った住宅を選びやすくなります。
地震保険の割引や住宅ローンの金利を引き下げられる
住宅性能表示制度で高い等級を取得すると、様々な経済的メリットを受けることができます。
例えば、耐震等級に応じて地震保険料が最大50%割引されたり、フラット35や民間金融機関の住宅ローンで金利の引き下げを受けられたりする場合があります。長期的に見ると大きな費用削減効果が期待できます。
紛争解決がしやすくなる
住宅性能評価書があることで、万が一トラブルが発生した際の紛争解決がスムーズになります。性能評価書は法的な証明書としての効力があるため、住宅の品質について客観的な判断基準となります。
また、指定住宅紛争処理機関による調停や仲裁などの制度も利用しやすくなります。
住宅性能表示制度を利用するデメリット
住宅性能表示制度を利用する際は、いくつかの課題についても理解しておく必要があります。高い等級を目指すほど建築コストが上がり、また評価書の取得にも費用が必要です。
設計の自由度が制限される場合もあるため、メリット・デメリットを総合的に判断することが重要です。
建築コストが高くなる
住宅性能表示制度で高い等級を取得するには、それに見合った性能を確保するための建材や工法を採用する必要があります。
例えば、高い断熱性能や耐震性能を実現するためには、より高品質な建材や施工技術が求められ、結果として建築コストの上昇につながります。
取得費用がかかる
住宅性能評価書を取得するには、設計段階と建設段階の2回の評価を受ける必要があり、それぞれに費用が発生します。
一般的な戸建住宅の場合、評価機関によって金額は異なりますが、両方合わせて15万円から20万円程度の費用がかかります。これは建築費用とは別に必要となる経費です。
設計デザインに限りがある
高い等級を取得しようとすると、構造や設備面での制約が生じる場合があります。例えば、採光や換気の基準を満たすために窓の位置や大きさが制限されたり、断熱性能を確保するために壁厚を確保する必要が出てきたりします。
デザイン性と性能のバランスを考慮する必要があります。
三鷹市で注文住宅を建てるなら大創建設がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 大創建設株式会社 |
| 住所 | 東京都三鷹市上連雀7丁目32番32号 |
| 対応エリア | 三鷹市・武蔵野市・調布市・小金井市・府中市・西東京市・杉並区・練馬区・世田谷区 |
| 公式サイト | https://www.daiso1966.jp/ |
大創建設は、住宅性能表示制度において高い評価を得ている工務店です。
特に耐震等級3や断熱等級5など、重要項目で高い等級を標準仕様としています。スーパーウォール工法による高い耐震性と断熱性を実現し、長期優良住宅の認定も多数取得しています。
性能とデザインの両立にこだわる三鷹市の方におすすめの工務店です。
大創建設株式会社の口コミや評判、特徴に関して、以下の記事で詳しく解説しています。同社について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
まとめ
住宅性能表示制度は、住宅の品質を客観的に評価できる重要な制度です。制度利用にはコストや制約も伴いますが、長期的な視点で見ると大きなメリットがあります。
マイホーム購入の際は、この制度を活用して、自分に合った性能を備えた住宅を選択することをおすすめします。