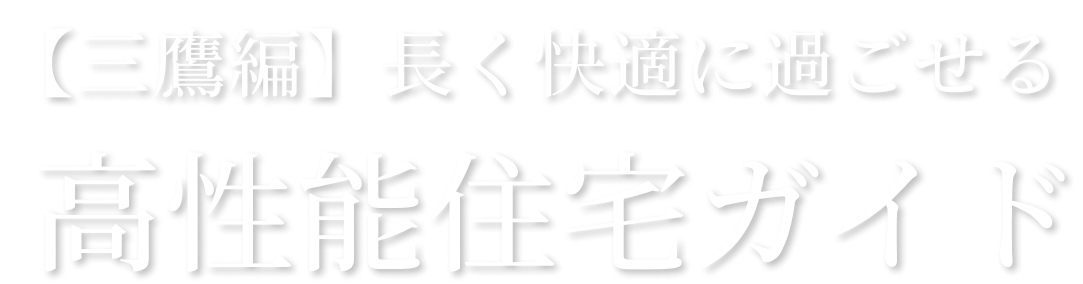「注文住宅にかかる費用ってどのぐらい??」
「資金計画のポイントってあるの?」
注文住宅で家を建てることは、人生において非常に高い買い物です。家を建てるときに必要になってくるのが、資金計画です。
どのぐらいの費用が、どのタイミングで必要なのか、また実際に費用が払っていけるのかも不安になる方もいるでしょう。資金計画については、念入りに立てることが重要です。
そこで本記事では、資金計画のポイントや注意点まで解説します。支払いのタイミングなども解説しますので、家づくりを検討している方は参考にしてみるといいでしょう。
また、以下の記事では当メディアが厳選する高性能にこだわる住宅会社を紹介しておりますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
資金計画の立て方
注文住宅で非常に大切になるのが資金計画です。資金計画は家を建てるための第一歩とも言えます。
資金計画の立て方としては、まず総予算を決めることです。総予算とは『自己資金』と『毎月の返済額』の合計です。まずは自己資金がどの程度あるのか把握しましょう。現状の年収や貯蓄額を把握しておくことが大切です。
総予算を決めたら、次に注文住宅にかかる費用を知っておきましょう。家を建てるとなると、建物本体だけでなく土地代や税金など様々な費用がかかります。
後に注文住宅にかかる費用の内訳も解説しているため、参考にしてください。そして、費用がどのタイミングで支払うかも把握するのが大切です。家を建てた後も、後悔しないような資金計画を立てましょう。
資金計画シミュレーションの手順
注文住宅の資金計画を成功させるには、具体的なシミュレーションが欠かせません。
以下の手順で進めることで、無理のない資金計画を立てられるでしょう。
これらの手順を踏むことで、現実的で持続可能な資金計画が完成します。
収入・支出・借入額を整理する
資金計画の第一歩は、家計の現状を正確に把握することです。
まず世帯の手取り収入を月単位で算出し、固定費と変動費を分けて整理してください。
固定費には住居費・保険料・教育費などが含まれ、変動費には食費・光熱費・娯楽費などが該当します。
現在の家計簿データを3か月分程度振り返り、平均的な支出額を把握しましょう。
次に借入可能額の算出を行います。一般的に住宅ローンの年間返済額は年収の25%以内が目安とされており、世帯年収600万円の場合は年間150万円、月額12.5万円程度が上限です。
ただし他の借入がある場合は、その返済額も含めて計算する必要があります。
返済計画とリスク管理設定をする
借入額が決まったら、具体的な返済計画を立てていきます。金利タイプ・返済期間・ボーナス返済の有無などを検討し、月々の返済額を無理のない範囲で設定することが重要です。
変動金利を選ぶ場合は、金利上昇リスクを考慮して現在の金利に1〜2%上乗せした条件でシミュレーションを行いましょう。
また返済期間は定年退職までに完済できる期間で設定するのが理想的です。
リスク管理では、収入減少や突発的な支出に備えた資金確保が必要になります。手取り月収の3〜6か月分を緊急予備資金として確保し、子どもの進学費用や家族の医療費なども想定しておくべきでしょう。
さらに住宅の修繕費として年間10〜20万円程度を積み立てることをおすすめします。
注文住宅にかかる全費用の内訳
注文住宅にかかる費用は、建物自体の費用だけではありません。土地の購入から家を建てるまで様々な費用がかかります。主に下記の3つの費用がかかります。
上記の3つの費用にプラスして土地代が注文住宅にかかる全費用です。それぞれ下記に解説していきます。
本体建築費用
本体建築費とは、建物そのものの建築にかかる費用をいいます。住宅購入における、全体の費用の約70%以上が本体建築費とされています。内訳として、以下のようなものがあります。
- 仮設工事
- 基礎工事
- 木工事
- 外装工事
- 内装工事
- 設備工事
- 設計費用
仮設工事とは、工事に必要な足場の組み立てや、仮設トイレ、駐車代などが含まれます。家を建てる前の準備から費用がかかってきます。
基礎工事、木工事、外装工事、内装工事、設備工事は、建物本体に関わる工事です。間取りやデザインによって工事費用は変わるため、建設会社の方ともしっかり確認しましょう。
また、設計費用は会社にもよりますが、3,000万円の木造住宅の場合は、工事費用全体の10〜15%が相場と言われています。
付帯工事費用
付帯工事費用とは、建物以外の工事にかかる費用のことです。総費用の15〜20%が付帯工事費用の目安とされています。内訳として、以下のようなものがあります。
- 外構工事
- 屋外設備工事
- 取り付け工事
- 解体工事
- 地盤工事
外構工事は、庭や駐車場などの工事のことです。庭の面積やデザインによっても費用が変わってきます。
屋外設備工事は、水道・ガス・電気などを家の敷地内まで引き込むための工事です。ガス管は一般的に1mごとに費用が高くなるため、敷地の大きさで変わってきます。取り付け工事は、カーテンや照明器具などの取り付け費用です。
解体工事は、中古の物件を購入した際に建物を解体してから新築を建てる場合に必要になります。また、地盤工事も地盤が弱い場合に、地盤調査や改良工事費用がかかってきます。
諸費用
諸費用とは、建築費以外の費用のことです。総費用の10%程度が目安とされています。
1つ1つと考えると少ない費用に見えても、合計すると予想以上の支出になるため注意が必要です。内訳として、以下のようなものがあります。
- 建築会社との契約にかかる費用
- 不動産取得や住宅ローンにかかる税金
- 保険料
- 引越し費用
建築会社と契約を行う際に、工事請負契約にかかる手数料や収入印紙代が費用としてかかります。建築会社や工務店によって費用は変わるのが実際です。
不動産取得や住宅ローンにも税金がかかります。代表的なものは、不動産取得税や登録免許税、固定資産税などです。
保険料は、住宅ローンに必要な火災保険や地震保険があります。近年では火災保険と地震保険がセットになっている場合が多いです。
引越し費用は、現在住んでいる場所から引越しする場合にかかる費用です。家具家電や日用品など家で使用するものも費用としてかかります。
費用を支払うタイミング
注文住宅の資金計画を建てる上で、費用を支払うタイミングを把握しておくと、計画的に資金を準備できます。費用の支払いタイミングについては、以下の4つがあります。
それぞれのタイミングについて見ていきましょう。
契約時
注文住宅の契約時には、建築会社との間で工事請負契約が締結され、その際に総工費の約10~20%を支払います。
契約時の費用についてはローンが利用できないケースもあるため、自分の資産から用意するのがおすすめです。工事請負契約の時点で着手金が支払えないと、契約が締結できず、工事を始められません。
着工時
契約してから着工が始められるタイミングでも、費用を支払います。着工時に支払われる費用は、材料の調達や初期工事の開始に必要な資金として欠かせません。
着工のタイミングでの費用は、全体の20%から30%程度に設定されることが多く、この支払いによって工事の進行が保証されることになります。
上棟時
上棟時に3回目の支払いタイミングとなりますが、工事の進捗状況としては基礎工事や構造が完成しつつある段階で、まだ家の全体像は見えないでしょう。しかし、この段階で総額の約30%が必要になります。
上棟での支払いが完了すると、完成するまで支払いが求められることはありません。そのため、初期段階に支払いができるように資金計画を立てることが重要です。
完成時
注文住宅が完成した時点で、契約金の残りの金額を支払います。それまでに支払った金額によって残額は異なるものの、おおよそ20~30%が必要です。
完成時には住宅ローンも利用できるため、資金準備には比較的余裕が持てるでしょう。建物が完成して契約金額の支払いまで完了すれば、家づくりの全てのプロセスが完了したことになります。
資金計画のポイント
上記で解説した通り、注文住宅で家を建てるには様々な費用がかかります。そのためにしっかり資金計画を立てることが大切です。資金計画のポイントとして以下があります。
上記のポイントを解説していきます。
自己資金を決める
自己資金とは、現在ご自身が所有しているお金のことです。自己資金がどの程度あるのか把握しておくことは、これから住宅ローンを借りる時や将来のライフプランに重要になってくるため、正しく把握しておきましょう。
注文住宅で家を建てるときの自己資金の目安は、購入価格の『20%以上』あるのが望ましいとされています。自己資金が0円の場合でも、フルローンで家を建てることは可能です。
しかし、将来のライフプランなどを考慮すると、20%以上の自己資金があると良いとされています。自身のライフプランにも合わせた自己資金を決めましょう。
自分に合った住宅ローンを見つける
住宅ローンでの借入可能額は、年収・返済期間・返済負担率が大きく影響します。また、頭金によっても借入額も変わってきます。
住宅ローンの上限は年収の6〜7倍とも言われています。住宅ローンを決める際は、自身が無理なく返せる金額はいくらなのか見極めてから、住宅ローンを選びましょう。
住宅ローンにも様々な種類があります。ライフプランをイメージして、返済期間や金利タイプを決めていきましょう。
また、誰の名義で借りるかもポイントになってきます。近年では、夫婦2人で共働きをしている家庭が増えているため、ペアローンという種類もあります。借入額を増やせる方法や、住宅ローン控除もあるため利用していきましょう。
頭金を用意する
頭金とは住宅ローンを組む際に最初に支払う金額であり、ローンの借入額を減らす効果があります。一般的に頭金の目安は、物件価格の10%から20%程度とされていますが、できるだけ多くの頭金を準備することで毎月の返済額を抑えることが可能です。
頭金を用意することで金融機関からの信用も高まり、より良い条件でローンを組める可能性が高まります。頭金の準備は日々の生活費を見直し、無駄な支出を削減することから始めると良いでしょう。
十分な頭金を準備することで、将来的な返済負担を軽減し、無理のない資金計画を立てることが可能です。事前に用意できる資金があれば、頭金として支払うのがおすすめです。
返済のシミュレーションを行う
毎月の返済額は、住宅ローンの借入額で決まります。住宅ローンをどの程度借入ができるのかをシミュレーションしておきましょう。
住宅ローンのシミュレーションは、銀行などのホームページなどでも簡単にできます。そこで現在の年収に対する年間返済額から、毎月の返済額が決まってきます。自身が無理なく返せる金額を見極めましょう。
また、住宅ローンも借りる場所によって様々です。シミュレーションもタイプ別に比較してみましょう。
税制優遇制度の活用
税制優遇制度とは、一定の条件を満たせば税金を少なくできる制度のことです。家を建てた場合に条件が満たされると、最大13年間の税額控除が受けられます。(2025年12月31日までの入居の場合)
減税額は、年末の借入残高によりますが、所得税額が限度となっています。控除額の少ない夫婦共働きのご家庭のほうが、減税額は多くなる可能性が高いです。
上手く税制優遇制度を活用することで、より費用を抑えられます。詳しいことは、建築会社や住宅ローンを借りる銀行などの専門の方に相談してみましょう。
資金計画の注意点
資金計画を建てるためには、注意点もあります。
上手く資金計画を立てるためにも注意点も確認しておきましょう。
余裕を持った資金計画を立てる
資金計画は余裕を持って立てましょう。現在の状況では住宅ローンも返せると思っていても、ライフプランによって住宅ローンが返せなくなる場合もあります。
例をだすと、出産によって妻が産休・育休休暇によって収入が不安定になることです。また、病気によって働けない場合も同様です。
しっかりライフプランにも合わせて、もしもの場合に備えておくことが重要です。余裕を持った資金計画を立てましょう。
専門家と一緒に資金計画を考える
注文住宅の資金計画を考える際は、専門家と一緒に進めましょう。
住宅購入は人生で最も大きな買い物の1つであり、高額な資金が動きます。しかも専門的な知識や複雑なプロセスが必要になるため、プロの助言を受けるのがおすすめです。専門家は資産状況や収入、将来のライフイベントを考慮に入れた現実的な計画を提案してくれます。
また、複雑な税制や補助金制度、ローンの種類や金利の選択など、素人では把握しづらい情報も専門家の知識を活用することで、適切な判断が可能になります。これらの情報を活用すると、費用面でも大きなメリットとなるでしょう。
専門家と相談することで、無理のない返済計画や将来的なリスクへの備え、安心して住宅購入に臨めます。資金計画をしっかりと立てるためにも、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
長期的なライフイベントを考慮する
注文住宅の資金計画は、長期的なライフイベントを考慮しなければいけません。
家を建てて暮らすとなると、10年単位で長期的な視点を持ち、その間に起こり得るさまざまなライフイベントに備える必要があります。例えば子どもの進学費用や親の介護、転職や収入の変動など、将来的に発生する可能性のある支出を見越しておくことが求められます。
これらの支出が必要になっても無理なくローン返済を続けられるよう、資金に余裕を持たせた計画を立てることが必要です。突発的な支出に備えて資金を確保することで、収入が減少してもローン返済を延長しなくて済みます。
家族構成やライフスタイルの変化によって、将来的に住み替えやリフォームが必要になることは避けられません。絶対にあり得ないということはないため、長期的なライフイベントを考慮して資金計画を立てましょう。
補助金・助成金の活用方法
住宅建築費用を軽減するため、国・東京都・三鷹市が提供する様々な補助金制度を活用しましょう。
複数の制度を組み合わせることで、大幅な費用削減が期待できます。
これらの制度を理解し、計画的に申請することで効果的な資金調達が実現します。
三鷹市の住宅関連補助金
三鷹市では省エネルギー設備の導入を支援する助成制度を実施しています。
新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金は、三鷹市環境基金を活用した制度であり、
高性能住宅に必要な設備導入時に活用可能です。
対象設備には太陽光発電システム・燃料電池・蓄電池・高効率給湯器・断熱窓への改修工事などが含まれます。
助成金額は設備の種類によって異なりますが、窓の断熱改修では工事費用の一定割合が支給される仕組みです。
また三鷹市住宅等防犯対策補助金も新設されており、防犯カメラの設置や防犯ガラスの導入に対して費用の一部を補助しています。
これらの制度は令和9年度まで実施予定のため、新築時に合わせて申請することをおすすめします。
東京都の住宅支援制度
東京都では環境性能の高い住宅を支援する包括的な制度を展開しています。
東京ゼロエミ住宅助成制度では、高い断熱性能と省エネ設備を備えた住宅に対して最大240万円の助成金を交付しており、高性能住宅を建築する際の強力な支援となるでしょう。
既存住宅省エネ診断・設計等支援事業では、省エネ診断や省エネ設計に係る費用の一部を補助しており、リフォーム計画の立案段階から支援を受けられます。
さらに既存住宅における省エネ改修促進事業では高断熱窓・ドア・断熱材・浴槽の改修工事に対して補助金を提供しています。
これらの制度は東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が窓口となっており、申請手続きや詳細な要件について相談が可能です。
複数の制度を組み合わせることで、より大きな費用削減効果が期待されるでしょう。
国の住宅支援制度
国レベルでは住宅の省エネ化を推進する大規模な支援制度を実施しています。
住宅省エネ2025キャンペーンでは、新築とリフォームを対象とした4つの補助事業により家庭部門の省エネ化を促進しており、子育て世帯に限らず全ての世帯が対象となります。
住宅ローン控除では子育て世帯・若者夫婦世帯が2025年に新築住宅に入居する場合、借入限度額が高く設定される優遇措置が継続されています。
認定住宅では5,000万円、ZEH水準省エネ住宅では4,500万円、省エネ基準適合住宅では4,000万円が上限となっており、最大13年間の控除を受けられるでしょう。
ただし2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられませんので、高性能住宅の建築が必須条件となっています。
これらの制度を活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減できるはずです。
ライフステージ別資金計画パターン
家族構成や年齢によって、最適な資金計画は大きく変わります。
それぞれのライフステージに応じた計画を立てることで、無理のない住宅購入が実現するでしょう。
各ステージの特徴を理解し、将来を見据えた資金計画を検討していきましょう。
新婚夫婦の資金計画
新婚夫婦の場合、将来の収入増加や家族構成の変化を見込んだ資金計画が重要です。
共働きであれば世帯年収が高い傾向にあるため、借入可能額も大きくなりがちですが、出産・育児による収入減少リスクを必ず考慮してください。
妻の産休・育休期間中は収入が大幅に減少するため、夫の収入のみで返済可能な金額に設定することをおすすめします。
世帯年収800万円の夫婦でも、夫の年収が500万円なら年間返済額は125万円程度に抑えるのが安全でしょう。
頭金については、結婚資金や新生活準備費用を差し引いた金額で検討します。将来の教育費積立も考慮し、手元資金を過度に減らさないよう注意が必要です。
また住宅ローン控除を最大限活用するため、控除期間中は繰上返済を控える選択肢もあります。
子育て世代の資金計画
子育て世代では、教育費の負担を考慮した資金計画が不可欠になります。
文部科学省の調査によると、高校卒業までの教育費は公立で約540万円、私立では約1,770万円が必要です。
住宅ローンの返済と教育費のピークが重ならないよう、返済期間や借入額を調整することが重要でしょう。
子どもが中学・高校に進学する時期は家計負担が増加するため、その期間の返済額を軽減できるよう計画しておくべきです。
頭金は教育費積立とのバランスを考慮して決定します。住宅購入により家計が圧迫され、教育費の準備が困難になっては本末転倒です。
児童手当は教育費として積み立て、住宅資金とは分けて管理することをおすすめします。
また、学資保険の活用も検討し、確実な教育資金確保を図りましょう。
40代夫婦の資金計画
40代夫婦の場合、定年退職までの期間を考慮した返済計画が最優先となります。
返済期間を65歳までに設定し、退職金での完済を前提とした計画は避けるべきです。安定した老後生活のため、住宅ローンは定年前に完済することが理想的でしょう。
収入がピークに達している年代のため借入可能額は大きくなりますが、老後資金の準備も並行して進める必要があります。
総務省の家計調査では、高齢夫婦世帯の平均的な生活費は月約22万円とされており、年金だけでは不足する分を自己資金で補う準備が重要です。
頭金は多めに用意し、借入額を抑制することで月々の返済負担を軽減します。また、変動金利よりも固定金利を選択し、将来の金利上昇リスクを回避する選択が賢明でしょう。
退職金の一部を繰上返済に充てる計画も立てておき、確実な完済を目指してください。
注文住宅を建てるなら大創建設がおすすめ

大創建設とは、三鷹市を中心に高性能な家づくりをしている建設会社です。創業55年以上の由緒ある建設会社であり、100年住める快適な住宅作りを目指しています。
今だけのお金の動きに合わせた焦点ではなく、将来のライフプランにも合わせた資金計画を立てることを大切にしている会社です。資金計画に不安がある方は、一緒に資金計画を立ててみましょう。
また、補助金や住宅ローンについても詳しいスタッフがいるため、ぜひ相談してみましょう。
大創建設株式会社の口コミや評判、特徴に関して、以下の記事で詳しく解説しています。同社について詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
まとめ
本記事では、資金計画のポイントや注意点を解説しました。
資金計画は家を建てる上で、1番重要なことです。現在のご自身に合わせたものではなく、将来のライフプランに合わせた資金計画を立てることをおすすめします。
また、本記事で紹介した大創建設も信頼できる会社になっています。自分で資金計画を立てることが不安な方や住宅ローン・補助金などの詳しい情報を知りたい方はぜひ見学会に参加し、相談してみましょう。
以下の記事では当メディアが厳選する高性能にこだわる住宅会社を紹介しておりますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。